仕事ができない社員の対応策とは?極端な能力不足への実践的マネジメントと法的対処
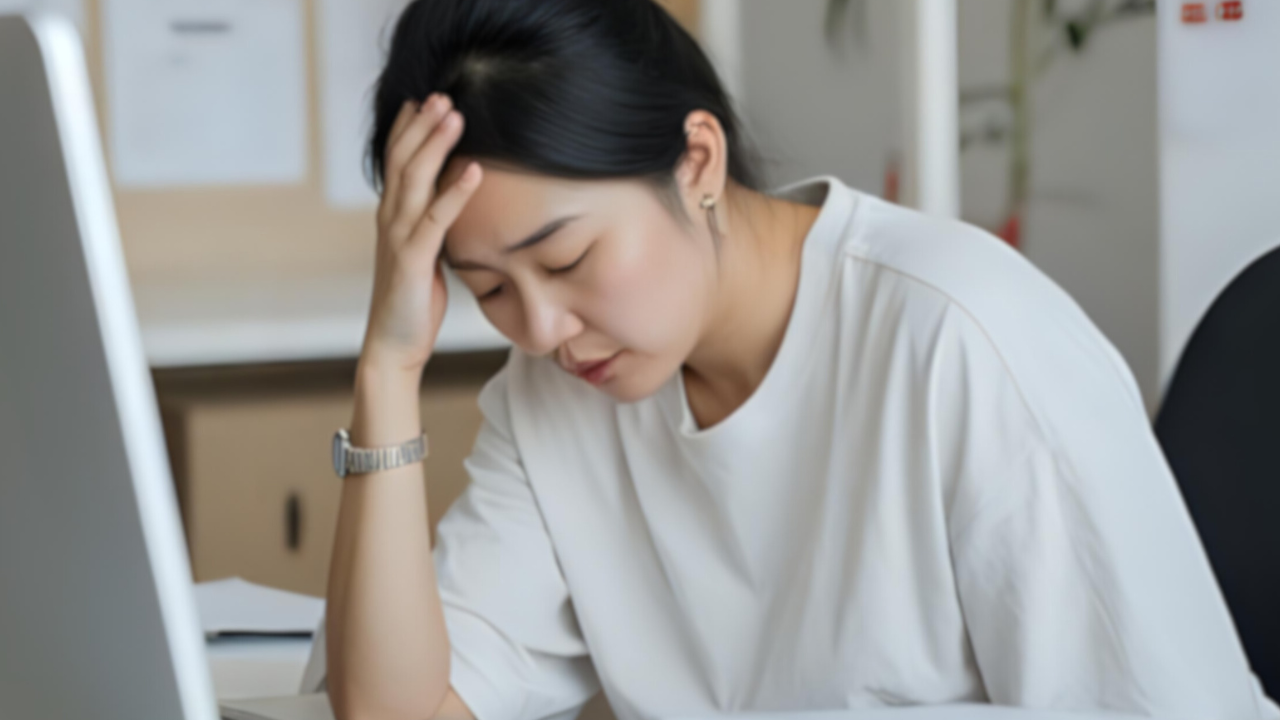
目次
動画解説
なぜ「すぐに退職や契約終了できないのか?」— 法的整合性の重要性
能力が極端に低く、仕事ができない社員に頭を悩ませている経営者の中には、「もう辞めてもらうしかない」と早期に結論づけてしまう方も少なくありません。しかし、雇用契約を解消するというのは、経営者の一存で自由にできるものではありません。労働契約法のもと、社員には雇用の安定が保障されており、企業側が一方的に契約を終了させるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であること」が必要とされます。
つまり、「能力が低いから」という主観的な判断だけでは足りないのです。その社員が労働契約で期待される水準の仕事を、どのように、どれだけ果たせていないのかという具体的な事実に基づいて説明できなければなりません。また、そのような社員に対して、どのような教育や指導の機会を与え、どれほどの期間努力してきたのかという経過も重視されます。
さらに注意すべきは、本人の納得感です。突然「能力不足だから辞めてくれ」と言われても、多くの社員は納得できません。「なぜこのタイミングで?」「だったらもっと早く言ってほしかった」と不信感を募らせ、トラブルに発展するリスクも高まります。そのため、解雇や退職の交渉を行う際には、事前のマネジメントが極めて重要です。
また、試用期間中であれば比較的柔軟な対応が可能です。なぜなら試用期間中は「本採用にふさわしいかどうか」を判断する期間であり、本人にも「まだ様子を見られている」という意識があるため、退職勧奨や本採用拒否について納得を得やすいのです。
このように、「辞めてもらう」という対応は、会社にとっても社員にとっても非常に重大な決断です。感情的に対応するのではなく、法的な整合性と納得のいくプロセスを意識することが、後々のトラブルを防ぎ、経営の信頼性を保つうえでも欠かせません。
「能力不足」とは何か?— 労働契約との関係から考える
職場で「能力が低い」「仕事ができない」と言われる社員がいると、どう対応すべきか悩む経営者や管理職の方も多いことでしょう。まず理解しておきたいのは、「能力不足」とは単なる主観的な評価ではなく、労働契約の文脈で明確に捉える必要があるということです。
労働契約とは、会社が報酬を支払う代わりに、社員が特定の業務を遂行するという法的な約束です。この契約に基づき、社員に求められる「能力」は、必ずしも絶対的な水準の高さではなく、「契約で予定されている業務を遂行する力があるかどうか」に集約されます。したがって、「能力不足」とは、労働契約で予定されている業務水準と、現実の業務遂行能力との間にギャップがある状態を指すと整理できます。
しかし、日本企業の多くでは、職種や業務内容を特定せずに社員を採用しており、育成を前提とした雇用も一般的です。このような場合、「労働契約で予定されている能力」が曖昧になりやすく、「今やらせている仕事ができない=能力不足」と直ちに断じるのは難しいことが多いのです。配置転換の可能性がある以上、現在の職務で成果が出ていなくても、他の業務で力を発揮する可能性もあるからです。
また、新卒や若手社員については「育成を前提とした雇用契約」と解釈されやすく、現時点での未熟さが直ちに「能力不足」とは見なされません。「今はできないが、将来的にできるようになることを期待している」という会社の姿勢が、労働契約の背景にあると判断されるためです。
一方で、職種・業務内容が明確に特定され、育成を前提としていない契約形態であれば、求められる能力も明確になりやすく、現実の業務成果との比較によって能力不足を判断しやすくなります。このような明確な基準があれば、マネジメントや最終的な退職・解雇判断の際にも説得力のある対応が可能になります。ただし、こうした雇用形態では、採用段階から高いスキルが求められるため、賃金水準を引き上げなければならないなど、別の課題も発生します。
いずれにしても、能力不足という評価を行うには、その根拠となる「事実」の把握と説明が不可欠です。「仕事ができない」というのは評価であり、評価の裏付けとなる客観的な事実がなければ説得力は生まれません。日々の業務の中で、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうした)に基づいて具体的な事例を蓄積し、社員の行動や成果に関する記録を残すことが、マネジメント上も、法的な観点からも極めて重要なのです。
能力不足の社員に対するマネジメントの基本方針
能力不足の社員に対して、どのように接し、育て、活用していくべきか。それは経営者や管理職にとって、極めて重要かつ難しい課題です。特に人材不足の今、すぐに退職や解雇に踏み切るという選択肢は現実的ではなく、まずは「マネジメントによる活用」を中心に据えるべきです。
採用した社員の育成・活用は、現場の上司や管理職、最終的には社長の仕事です。採用に失敗した、では終わらせず、その人をどうやって戦力にできるかを考えることが経営者の責任です。そして、能力不足の社員には特に「具体的・丁寧な教育指導」が求められます。抽象的なアドバイスや「自分で考えろ」という丸投げでは、理解も実践も難しく、結果としてマネジメントの放棄につながります。
基本的にはマイクロマネジメントを意識すべきです。新入社員に対して行うような、一つ一つ具体的な行動まで踏み込んだ指導を、ある程度長期にわたって続けることが必要です。例えば、マニュアルを作成したり、目の前で実演して見せたりするなど、視覚的・体験的に仕事のやり方を伝える方法も有効です。
また、業務日報や面談記録、指導履歴などを通じて、教育の経緯と成果・課題を「記録」として残すことも忘れてはなりません。これは、社員本人の理解を促すだけでなく、後にトラブルとなった際の説明や立証にもつながる重要な資料となります。
社員の「得意・不得意」を見極めて、向いている仕事に配置転換を行うことも、柔軟な対応策の一つです。ただし、企業規模によっては異動先がない場合もあるため、その現実的な限界も認識する必要があります。
なお、能力不足の社員のマネジメントには、一定のストレスと負担が伴うことも事実です。上司や周囲の社員が消耗して、職場全体の士気が下がったり、逆に当該社員自身が適応障害などを引き起こすこともあります。こうした点も踏まえた上で、会社としての「持続可能なマネジメント体制」を構築することが求められます。
退職勧奨の進め方
能力不足の社員に対して、最善のマネジメントを尽くしてもなお改善が見られず、かつ業務に大きな支障をきたしている場合、退職を提案する「退職勧奨」を検討することになります。これは会社としても本人としても苦渋の選択ですが、他の社員への悪影響や組織の健全性を考慮すれば、やむを得ない判断となることもあります。
退職勧奨の基本は、「本人の納得を得ること」に尽きます。法的には、退職勧奨はあくまで「話し合い」による合意を前提としたものであり、強制することはできません。そのため、準備と伝え方には細心の注意が必要です。
まず重要なのは、辞めてもらわざるを得ない「理由」の説明です。ただ「仕事ができない」ではなく、どのような問題が、どのような事実に基づいて発生しているのかを具体的に伝えることが求められます。「◯月◯日にはこういった業務ミスがあり、その後の改善も見られなかった」「このまま任せると職場の混乱や顧客への悪影響が避けられない」といったように、評価ではなく「事実」を中心に説明します。
次に、退職の条件についても明確に提示します。退職日、金銭的な支援(退職金、特別手当など)、退職理由の取り扱い(自己都合か会社都合か)、有休消化の可否など、本人が不安に思う点を事前に整理して、丁寧に説明できるようにしておきましょう。交渉が難航するようであれば、弁護士のサポートを得ることも選択肢となります。
特に試用期間中であれば、本人も「まだ本採用ではない」という認識があるため、退職の提案が受け入れられやすい傾向があります。そのため、能力不足が明らかになった場合は、試用期間中の対応を優先的に検討するのが望ましいと言えます。
注意点として、退職勧奨を「強制」と誤解されるような対応は絶対に避けなければなりません。強い言葉や高圧的な態度、選択肢を与えないような一方的な通告などは、後にトラブルや法的リスクを引き起こす原因となります。あくまで「選択肢の提示」「事実に基づく対話」を基本に、丁寧に、かつ冷静に話し合いを進めることが必要です。
解雇・本採用拒否の法的留意点
退職勧奨に応じてもらえなかった場合や、そもそも改善の見込みが極めて乏しいと判断された場合、最終手段として「解雇」や「本採用拒否」を検討することになります。ただし、これらは労働者の地位を直接的に奪う行為であり、法的なハードルが非常に高く設定されています。慎重な対応が求められます。
まず前提として、試用期間中であっても「労働契約」はすでに成立しています。したがって、試用期間中に行う「本採用拒否」も、法的には「解雇」に該当します。そのため、解雇と同様に「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされ、これを会社側が証明できなければ、不当解雇と判断されるリスクがあります。
この「合理的な理由」とは、主観的な評価ではなく、客観的な事実に基づくものである必要があります。例えば、具体的な業務ミスの内容や頻度、改善指導の有無とその効果、本人の対応姿勢などを、記録や証拠として蓄積しておくことが重要です。面談記録、指導記録、業務評価表、日報、同僚や上司からのフィードバックなどが、有力な証拠となります。
また、日頃の人事評価が「普通」や「高評価」となっている場合には、「能力不足」を理由とした解雇が矛盾してしまう可能性があるため、評価の整合性も意識しなければなりません。よくあるのが、「波風を立てたくない」「本人が不満を言いそうだから」といった理由で、事実に反した評価を付けてしまうケースです。こうした評価の積み重ねは、後に会社側の主張を弱めてしまうことになります。
さらに、解雇に至るまでのマネジメントが不十分であると、会社側の誠実な対応が欠けていたと判断され、不当解雇とされる可能性が高くなります。「改善に向けて相応の機会を与えたか」「具体的な指導を行ってきたか」といった点は、裁判などでも重要な争点になります。
したがって、能力不足を理由とした解雇を検討する場合、必ず事前のマネジメントと証拠の蓄積を徹底し、法的リスクを十分に踏まえた上で対応を進める必要があります。場合によっては、社労士や労働法に強い弁護士と連携し、法的妥当性を確認しながら慎重に手続きを進めていくのが望ましいと言えるでしょう。
損害賠償請求はできるのか?
能力が極端に低く、仕事上のミスを繰り返す社員が、会社に損害を与えることは現実問題として起こり得ます。例えば、重大なミスによって取引先との関係を悪化させてしまったり、車両事故などで高額な損害を発生させてしまうようなケースです。こうした場面で「本人に損害賠償を請求できないのか」と考える経営者も多いと思います。
しかし、法的にはそのハードルは非常に高く設定されています。なぜなら、多くのケースでは、本人に「故意」があったわけではなく、「過失」あるいは「能力不足」が原因であることがほとんどだからです。特に、雇用契約のもとで働く従業員には、「労働によって利益を生み出すリスク」と「ミスによって損失が生じるリスク」を一定程度、会社が受け入れる前提があります。
このため、たとえミスによって会社に損害が生じたとしても、本人に全額の賠償責任を負わせることは原則として困難です。裁判で認められたとしても、その賠償額は損害全体のごく一部にとどまることが多く、逆に請求する過程で社員との関係が悪化したり、周囲の士気が下がるリスクの方が大きくなる場合もあります。
また、本人ではなく「身元保証人」に請求したいと考える企業もありますが、これも同様に法的な制限があり、本人よりもさらに限定された責任しか認められないケースがほとんどです。特に近年は、身元保証契約に関する判例も厳格化しており、保証人に実質的な請求を行うことは極めて難しくなっています。
結論としては、損害が発生した際の対処は「賠償請求」ではなく、あくまで「再発防止策」や「適切な配置・教育によるマネジメント」で対応するという姿勢が基本です。繰り返しになりますが、問題のある社員をマネジメントするのは会社の責任であり、「まさか、ここまでとは思わなかった」と後から言っても、経営の責任は免れません。
したがって、損害発生のリスクを最小限に抑えるためにも、適切な業務の割り振り、明確な指示、早期のフィードバック、そして必要に応じた配置転換など、日頃から丁寧なマネジメントを積み重ねることが何より重要となります。
おわりに
能力が極端に低く、仕事ができない社員への対応は、企業にとって非常に難しい課題です。一人の社員を辞めさせるかどうかだけの問題ではなく、職場全体の士気、教育体制、採用戦略、そして将来的な企業の成長力にも関わる、広範なマネジメントの問題でもあります。
大切なのは、安易に「辞めさせる」ことを選択肢の中心に据えるのではなく、まずは「どうすれば活かせるか」「どうすれば育てられるか」を真剣に考える姿勢です。そのうえで、どうしても対応が困難な場合に限って、退職勧奨や解雇といった法的手段を選ぶという順序が基本です。
そして、仮に損害が生じた場合にも、責任を問う前に「なぜそのような結果になったのか」「経営・マネジメント上に見落としはなかったか」を検証し、企業としての再発防止策を講じることが求められます。
人材の多様化や人手不足が深刻化する中、すべての社員が高い能力を持つとは限りません。しかし、それぞれの特性に応じて力を発揮できるよう支援することが、これからの企業経営における鍵となるでしょう。












