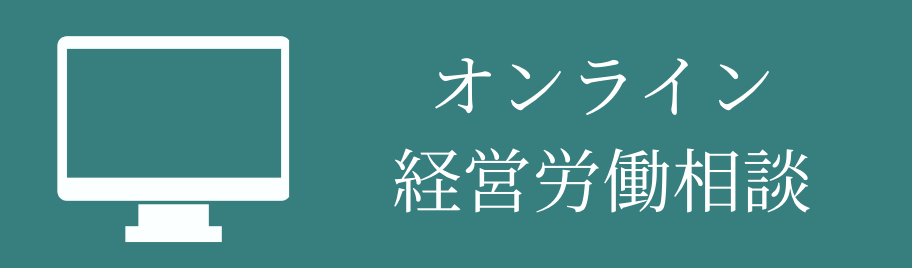能力が極端に低く仕事ができない社員への対処法|採用・マネジメント・解雇の正しい進め方

目次
動画解説
能力不足とは何かを正しく理解する
職場において「能力が低く仕事ができない社員」への対応は、経営者にとって大きな課題となります。とはいえ、単に「能力が低い」「仕事ができない」という印象だけで判断してしまうと、誤解や不適切な対応を招きかねません。まず重要なのは、「能力不足」という言葉の意味を正確に理解することです。
労働契約における「能力」とは、給料を支払う代わりに会社が期待している仕事を遂行する力のことを指します。つまり、「能力が不足している」と評価される場合、それは抽象的な能力の高さや一般的なスキルの話ではなく、「労働契約上、求められる業務が遂行できていない」という状態を意味します。
この観点から見ると、問題の核心は「能力が高いか低いか」ではなく、「任せた仕事ができているかどうか」です。たとえ一般的な基準で能力がそれほど高くなくても、会社が期待する業務を問題なく遂行できていれば、実務上は「能力不足」ではないと言えるのです。
この点を混同してしまうと、過度な要求や不当な評価が生じやすくなります。たとえば「仕事ができない」と感じたとしても、それが具体的にどの業務で、どのような場面で、どのように問題があったのかを明らかにしなければなりません。つまり、能力不足かどうかを判断するには、「求めている業務」と「現実の業務遂行能力」のギャップを具体的に認識し、明確にする必要があります。
これが、後の教育指導やマネジメント、さらには退職勧奨・解雇などの判断においても非常に重要な土台となるのです。感覚的・主観的な評価ではなく、契約上の期待と現実との間にどれだけの乖離があるか。その理解が、適切な対応の第一歩となります。
日本型雇用における「能力不足」の判断の難しさ
「能力不足かどうか」を判断するには、会社がその社員に何を期待していたか、すなわち労働契約で予定されていた業務内容や職務遂行レベルがどれほど明確だったかが重要になります。しかし、日本の多くの企業では、こうした期待値が非常に曖昧なまま採用が行われているのが実情です。
典型的なのは、職種や担当業務を特定せずに採用する「総合職型」の雇用です。入社時には「何でもやってもらう可能性がある」として幅広く採用し、その後、本人の適性や会社の都合で配属や業務内容が決まっていきます。このような雇用形態では、「今任せている仕事ができない=能力不足」と単純に言い切ることができません。なぜなら、他の業務であれば適性があるかもしれないからです。
さらに、新卒採用や若年層の採用では、「育成を前提としている」ことも多く、現時点で業務がうまくできないからといって直ちに「能力不足」と評価するのは難しい面があります。企業側が「いずれ育てていくことを前提に雇った」と見なされる場合、短期間の業務遂行能力だけをもって問題とするのは不適切とされかねません。
このように、日本型雇用においては「能力不足かどうか」の判断そのものが非常に難しい構造になっています。そのため、「何ができていて、何ができていないのか」「会社として何を求めていたのか」「今後改善可能なのか」といった点を丁寧に整理し、明文化しておくことがマネジメント上非常に重要です。
マネジメントでの対応が基本になる理由
能力が極端に低く、仕事ができない社員を抱えたとき、最初に考えるべきは「どう辞めさせるか」ではありません。むしろ、「どうやって育て、戦力に変えていくか」が第一に検討すべきテーマです。なぜなら、労働契約は給料を支払う代わりに、社員に仕事をしてもらう契約であり、雇用した以上は最大限に活用する責任が会社側にもあるからです。
人材の確保が困難な現代では、「できなければ辞めさせればいい」という発想では立ち行かなくなっています。採用はコストも時間もかかる上、必ずしも能力の高い人材を確保できるとは限りません。こうした背景からも、まずは今いる社員の中でどれだけ能力を引き出せるか、適材適所を見つけられるか、という視点が重要になります。
さらに、能力不足の問題は、本人の責任だけではなく、管理職や組織全体のマネジメントの問題でもあります。教育指導の仕方や業務の割り振り、成長の機会の与え方によっては、劇的にパフォーマンスが向上するケースもあります。特に新入社員や未経験者の場合、「いずれ成長すること」を前提に雇っているのが日本の一般的な雇用慣行ですから、初期段階の能力不足は当然のことと考えるべきでしょう。
このように、「辞めさせる前にやるべきことがあるか」を常に問い、教育指導や配置転換などのマネジメントによる改善可能性を十分に検討する姿勢が、労務管理上も、組織の健全性という点でも、不可欠なのです。
具体的な教育指導とマイクロマネジメントの必要性
能力が極端に低く、仕事がうまくできない社員に対しては、通常のマネジメントでは効果が出にくいケースが多く見られます。そのため、より丁寧で具体的な教育指導、いわゆるマイクロマネジメントが求められます。
こうした社員は「何をどうすればよいか」を自分で判断する力が弱いことが多く、抽象的な指示や「自分の頭で考えて動け」というスタイルでは理解も行動もできません。その結果、期待された業務成果が出せないだけでなく、本人の自信喪失や職場の混乱にもつながってしまいます。だからこそ、業務内容を細分化し、具体的な指示を段階的に与えながら仕事を覚えてもらうアプローチが有効なのです。
例えば、新入社員のように、業務フローを一から説明したり、目の前で手本を示したり、行動の一つ一つに対してフィードバックを与えたりすることが必要です。また、マニュアルやチェックリストを用いて、繰り返し確認できるようにすることで、理解と定着を助ける工夫も求められます。
このような対応は手間がかかりますが、マネジメントの本質は「相手のレベルに応じた適切な指導をすること」です。適切な指導をせず、結果だけを求めたり、放置したりすることは、管理職自身の職務放棄とも言えます。
特に試用期間中であれば、こうした具体的な教育指導を集中的に行うことで、育成の可能性を見極めると同時に、本人の成長も促すことが可能です。長期的に見ると、初期の手間がその後の安定的な戦力化につながることも多いため、マイクロマネジメントは避けるのではなく、必要な戦略として積極的に取り組むべきなのです。
他業務への配置転換の検討
業務能力に課題がある社員であっても、必ずしもすべての仕事ができないわけではありません。現状の職務に適性がないというだけで、他の業務では能力を発揮できる可能性があるため、配置転換は重要な選択肢の一つです。
特に企業規模が一定以上ある場合、他部門や異なる職種での再チャレンジの場を設けることで、本人の持ち味を活かせるケースがあります。例えば、対人業務でミスが多い社員でも、裏方の業務で正確さを発揮できることは珍しくありません。逆に事務作業が不得意でも、体を動かす作業ではスムーズに対応できるといったパターンもあります。
配置転換を検討する際のポイントは、「実際に異動可能な現実的なポジションがあるかどうか」と「本人が希望や適性を感じている業務かどうか」です。本人の申告に一定の耳を傾けつつ、現場の受け入れ体制や業務内容とのマッチングを客観的に判断する必要があります。
また、配置転換には会社側の配慮義務と裁量のバランスが問われる場面もあります。配転命令が無効とされないためには、「現職での勤務継続が困難である理由」と「新しい業務が本人の能力・経験に照らして無理がないこと」の説明が求められます。無理な配転でさらにパフォーマンスが悪化したり、メンタル不調を引き起こしたりするリスクもあるため、慎重な対応が不可欠です。
とはいえ、配置転換によって本人も周囲も負担が軽減され、組織全体がより良いバランスで機能するようになるのであれば、それは非常に有効なマネジメント施策となります。多様な働き方が求められる現代において、個々の適性に応じた業務再設計は、企業の柔軟性と競争力を高める鍵とも言えるでしょう。
職場全体への悪影響と早期対応の重要性
能力が極端に低く、仕事ができない社員が職場に存在し続けると、当人だけの問題にとどまらず、周囲の社員や職場全体に深刻な悪影響を及ぼすようになります。特に、上司や同僚が継続的にフォローを強いられたり、業務のしわ寄せを受けたりする状況が長引くと、職場の士気や生産性が低下しやすくなります。
最初のうちは周囲も善意でフォローに努めますが、状況が改善されなければ「なぜあの人だけ特別扱いされているのか」「自分ばかり負担が大きい」といった不満が蓄積していきます。やがてそれは組織内の不公平感や不信感に繋がり、他の優秀な社員の離職リスクを高める要因にもなりかねません。
また、本人にとっても、自分が周囲の足を引っ張っていることを感じながら働き続けるのは大きなストレスです。場合によっては、適応障害などのメンタル不調を引き起こす可能性すらあります。「頑張っているのに成果が出ない」「評価されない」という状況が長く続けば、自尊心を失い、職場への定着がますます困難になります。
こうした悪循環を避けるためには、問題の早期発見と適切な初動対応が何より重要です。「しばらく様子を見る」という対応は、時として状況を悪化させ、取り返しのつかない問題に発展させることもあります。特に試用期間中であれば、観察と記録を徹底し、必要な対処をタイミングよく行うことが、本人と会社の双方にとってベストな結果をもたらします。
社員一人の問題が、周囲にどのような影響を与えているか、職場全体を視野に入れた冷静なマネジメントが求められます。
採用と配置の工夫によるリスク回避
「能力が極端に低く、仕事ができない社員」という問題に直面した企業では、その後の採用方針や人材配置を見直すことが重要です。なぜなら、こうした問題の多くは、採用段階でのミスマッチや、入社後の配置・育成の不備が背景にあることが多いためです。
まず採用時点では、単に履歴書や面接の印象だけで判断するのではなく、実務に即したスキルチェックや、ロールプレイなどを取り入れ、客観的に業務遂行能力を確認する工夫が必要です。特に「最低限このレベルには達していてほしい」という水準を明確に定義し、それに満たない場合には採用を見送る判断が求められます。
また、採用に際しては「育成を前提とした人材」と「即戦力を期待する人材」を明確に分けて募集・選考することが、採用後のトラブルを避けるうえで有効です。仮に育成を前提とするのであれば、入社後の研修体制やOJT体制を整備し、成長をサポートする前提条件をしっかりと整えておかなければなりません。
次に、配置の工夫も重要なポイントです。社員によって得意・不得意の分野が異なるのは当然であり、現在任せている仕事ができないからといって、必ずしも能力不足と断じることはできません。現実的に異動可能な範囲で、他の部署や職務に適性があるかどうかを見極め、柔軟に配置転換を行うことで、本人の能力を活かす道が見つかるケースもあります。
企業規模や業種によっては異動先の余地が少ないこともありますが、限られた中でも選択肢を模索し、可能な限り「適所」を見つけていくことが、人材を有効活用するうえでの経営努力のひとつです。
採用段階から「何を期待し、どのように活用していくか」を具体的に描くこと。そして、入社後も状況に応じた柔軟な配置やサポートを行うことが、能力不足リスクを最小限に抑えるための鍵となります。
退職勧奨・本採用拒否・解雇を進める際の留意点
退職勧奨や本採用拒否、解雇といった最終手段を取る際には、法的な手続きと実務的な配慮の両面を慎重に進める必要があります。まず大前提として、これらはあくまでも「マネジメントや配置転換、教育指導を尽くしたが、どうにも改善が見込めない場合」に限られるべき対応です。雇用契約は、企業が給料を支払う代わりに社員が労務を提供するというものである以上、一定のパフォーマンスが求められますが、それでも安易に雇用を打ち切ることは認められていません。
退職勧奨を行う際には、感情的に「辞めてくれ」と伝えるのではなく、あくまでも冷静に具体的な問題点や、その改善が見込めなかった経緯を説明したうえで、話し合いによって合意を目指すことが重要です。特に試用期間中にこの話を持ちかける方が、本人にとっても納得感を得やすく、後々のトラブルを避けやすくなります。逆に、本採用後に突然その話を持ち出すと、「今さらなぜ?」という不信感を招き、話し合いが難航することもあります。
また、退職勧奨に応じてもらえなかった場合には、本採用拒否や解雇という選択肢も視野に入ります。ただしこれらは、法的に「解雇」に該当し、労働契約法上の「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。たとえ能力不足が明らかであっても、そのことを裏付ける客観的な証拠や、改善のための取り組みの記録などがなければ、解雇が無効と判断されるリスクがあります。
さらに、現場でよく見かけるのが、マネジメントの中での誤った対応が逆に問題をこじらせるケースです。たとえば、日頃は褒めてばかりだった社員に、ある日突然「もうダメだ」と告げるようなやり方では、納得も得られずトラブルにもなりやすい。そうではなく、日常的に適切なフィードバックを行い、改善のチャンスを与えたうえで、それでも成果が見込めなかったというプロセスがなければなりません。
本採用拒否や解雇を行う際は、可能であれば退職合意書の締結などによって、後々の紛争を予防することも考えておくべきです。また、少しでも不安がある場合には、弁護士などの専門家に相談し、法的な観点からも妥当性を確認したうえで進めることが安全です。
雇用を打ち切るということは、会社にとっても当事者にとっても大きな決断です。だからこそ、感情ではなく、事実と記録、法的要件をもとに、丁寧かつ慎重に進めていく姿勢が何より重要なのです。