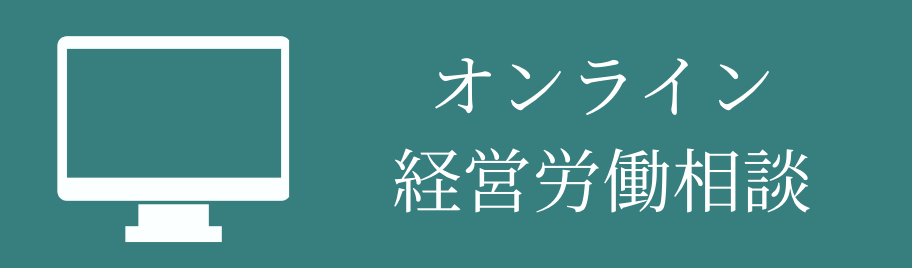横領が発覚した経理担当者が「年休消化で即退職」と言い出したら?企業側が取るべき実務対応と法的ポイント

目次
動画解説
横領発覚と同時に退職を申し出る社員への初期対応の考え方
経理担当者など、会社の財務に深く関わる立場の社員が業務上の横領を行い、その発覚と同時に「年次有給休暇を消化して退職する」と申し出た場合、企業としては極めて難しい対応を迫られることになります。とくに「信頼していた社員による横領」というショックに加え、事実関係の調査に協力しないまま、退職届と年休申請を一方的に提出してくるケースでは、感情的な混乱も招きやすく、冷静な判断が求められます。
まず重要なのは、企業として「何を明らかにしなければならないのか」という目的を見失わず、適切に初動を組み立てることです。今回のようなケースでは、社員本人が出社せず、調査への協力を完全に拒否しているため、社内での事情聴取が困難です。このような状況下で「調査に協力するよう強制できないか」という視点を持つことも理解できますが、実際には、協力の意思がない社員に無理に出社させたり、聴取を強行したりすることは法的に難しく、現実的な手段ではありません。
退職までの期間が有給休暇で埋まっており、社員がそれを取得する意思を示している場合、「時季変更権」の行使も検討されることがあります。しかし、時季変更権とは本来、別の日に有休を取るよう変更を求めるものであり、退職日までに代替日が存在しない場合には、その行使自体が不可能となることも多く、結果的に実効性がありません。
このように、当該社員に対して調査協力を強く求めることができない状況下では、あくまで「できる範囲での調査」と「企業としての対応方針の整理」が求められます。感情的に振り回されず、証拠や事実に基づいた判断を行うことが、企業側のリスクを最小限に抑える第一歩となります。
年次有給休暇の取得と時季変更権の実効性の問題
社員からの年次有給休暇(以下、年休)の申請があった場合、会社にはこれを尊重する義務があります。ただし、業務に著しい支障があるときは「時季変更権」を行使して、年休の取得時期を変更させることが可能です。とはいえ、実際に横領が発覚した直後の社員が「退職までの期間、年休をすべて消化する」と言ってきた場合、その対応は非常に難しくなります。
今回のように、すでに退職日が決まっており、その日まで年休で日程がすべて埋まっている場合には、そもそも年休を「他の日に変更させる」ことができません。時季変更権の趣旨は、「別の日に取ってください」と指示することであって、「取得そのものを拒否する」ことはできないのです。そのため、会社として「この時期は出社してほしい」と申し入れたとしても、代替日が存在しなければ時季変更権の行使は実質的に不可能となります。
また、仮に形式的に時季変更権を行使できる余地があったとしても、本人が出社に応じない以上、実効性は著しく低くなります。「私は出社して調査に協力します」といった意思表示がないかぎり、制度的に年休の取得を制限しようとしても、現実には何の解決にもつながらないのが実情です。
このような背景から、年休の取得をめぐる議論で状況の打開を図るよりも、現実的には別の手段で対応していく必要があります。つまり、年休の取得自体を問題にするのではなく、調査の進め方や会社としての方針決定に焦点を移し、全体像の把握と次の対応策を冷静に組み立てていくべき局面なのです。
調査に協力しない社員への対応と独自調査の進め方
横領の事実関係を確認するためには、本人からの事情聴取が重要となるのは言うまでもありません。しかし、今回のように当該社員が出社を拒否し、調査への協力を完全に拒む場合、企業としては「本人がいなくても進められる調査方法」を検討せざるを得ません。
まず考えられるのが、「質問状」を作成し、聞き取りたい内容を整理したうえで文書として郵送またはメールで送付する方法です。本人が回答するかどうかは不確実ですが、少なくとも企業として説明の機会を与えたことの証拠になります。また、回答の有無や内容自体も今後の判断材料となり得るため、調査手続きの一環として十分に意味があります。
さらに、社員本人の協力が得られない場合でも、経理上の記録や口座の動きなど客観的な情報から事実を検証することが可能です。このような独自調査を行うには、顧問税理士や会計士の協力が非常に有効です。企業内の帳簿や領収書、振込記録などを第三者的な視点で確認してもらい、横領の痕跡や不審な取引がないかを洗い出していく作業が必要となります。
本人への事情聴取ができないからといって、すべての調査を諦める必要はありません。むしろ、客観的な証拠や関係資料を丹念に精査し、必要に応じて専門家の力を借りることで、本人の供述がなくとも相応の事実関係を明らかにすることは十分可能です。こうした調査が、後の懲戒処分や損害賠償請求の根拠として重要な役割を果たすことになるため、粘り強く対応していくことが求められます。
懲戒解雇の可否とそのタイミングに関する実務的な留意点
経理担当者による業務上横領が疑われるケースでは、企業秩序を著しく乱す行為として「懲戒解雇」を検討する企業も多くあります。とくに、会社のお金を管理する立場にある者が信頼を裏切る行為をしたとなれば、その処分は厳正なものでなければならないとの判断も当然と言えるでしょう。
もっとも、実際に懲戒解雇を行うには、いくつかの法的な要件や実務上のハードルがあります。まず確認すべきは、就業規則に懲戒解雇の事由として「業務上横領」などの行為が明確に記載されているかどうか、そしてその就業規則が周知されているかどうかです。これらが整っていれば、横領行為が確認された時点で懲戒解雇は原則として有効とされる可能性が高くなります。
しかしここで問題となるのが「退職の申し出」との関係です。無期雇用の正社員であれば、本人が2週間前に退職の意思表示をすれば、法的にはその日をもって退職することが可能です。つまり、退職の申し出がなされた時点から、企業側は懲戒解雇を実行するか否かの判断を、遅くともその2週間以内に下さなければならないのです。
この短期間で十分な調査を行い、懲戒解雇の根拠を固めることは容易ではありません。特に本人が事情聴取に応じない場合は、証拠収集の手段が限られ、判断に迷うこともあるでしょう。とはいえ、質問状を通じた対応や、独自調査の結果などを踏まえれば、懲戒解雇に踏み切る判断材料を得られる可能性もあります。また、本人が質問状にまったく反応しない場合には、「反論できない=認めた」と解釈されるリスクを本人が負うことになります。
懲戒解雇の実施に際しては、就業規則上、懲戒委員会の開催などの手続きを必要とする企業もあるため、そうした内部ルールに沿って進めることも忘れてはなりません。法的な要件を満たさずに処分を進めてしまうと、後に無効と判断されかねないため、慎重な手続きが求められます。
退職届の受理と懲戒解雇の選択肢の見極め
横領が疑われる社員から退職届が提出された場合、企業としては「退職を認めるか」「懲戒解雇とするか」という選択を迫られることになります。この判断は、単に手続き上の問題ではなく、企業のコンプライアンス方針や将来への影響も含めた重要な経営判断となります。
まず、退職届が提出された時点で、企業側がその内容を承認すれば、労働契約はその日をもって終了します。仮にその退職の申し出が「合意退職」の提案にすぎないとしても、会社側が承諾すれば法的には成立し、原則として撤回はできません。つまり、「この日付での退職を認めます」と言えば、その時点で労働関係は円満に終了することになるのです。
このように退職で事態を収める選択肢がある一方で、「企業秩序を重視し、横領の事実がある以上、懲戒解雇とすべきではないか」という判断をされる経営者の方も少なくありません。とくに組織の内部統制や他の従業員への示しを重視する会社では、懲戒解雇に踏み切ることが「当然の対応」とされることもあるでしょう。
他方で、小規模な企業などでは「懲戒解雇の準備にかけられる時間もリソースも限られている」「退職してもらえるのであれば、それ以上の対応は不要」「むしろ被害金の回収に注力したい」といった判断も現実的です。懲戒解雇にこだわるよりも、迅速な損害回復を優先する姿勢が会社の実情に合っているというケースもあります。
このように、退職の受理か懲戒解雇かという判断に「正解」はありません。企業の規模や方針、事案の内容などを踏まえたうえで、冷静かつ戦略的に判断する必要があります。判断に迷う場合には、弁護士と対話をしながら、社内事情や社風に即した方針を整理し、最終的な決断を下すことが望ましいと言えるでしょう。
懲戒解雇と退職金不支給の関係とその検討ポイント
問題社員への対応を検討する際、「退職金を支給すべきかどうか」は経営者にとって非常に重要な論点の一つです。とくに業務上横領など重大な背信行為が疑われる場合、「このような社員に退職金を払うのは納得できない」と感じるのは当然の感覚でしょう。実際に、退職金の支給は義務ではなく、就業規則や退職金規程に基づく契約上の給付であるため、一定の条件を満たせば「不支給」とすることも可能です。
多くの企業の退職金規程では、「懲戒解雇事由があるとき」や「会社の名誉を著しく毀損したとき」などを退職金の不支給事由として定めていることが一般的です。重要なのは、実際に懲戒解雇処分を行わなくても、「懲戒解雇に相当する行為があった」と判断されれば、不支給の対象となり得る点です。つまり、形式的な処分の有無にかかわらず、就業規則上の要件を満たしていれば、退職金の支給を拒否する法的根拠は存在します。
一方で、古い規程のまま運用されている会社では、いまだに「懲戒解雇した場合に限る」といった記載が残っていることもあります。このような場合には、実際に懲戒解雇の処分を行わないと退職金を不支給にできない可能性があるため、規程の確認と法的解釈が必要になります。場合によっては、他の条項を適用できないか、あるいは懲戒解雇を急ぐべきかといった視点から、弁護士とともに慎重に検討する必要があります。
退職金の支給をめぐっては、企業の対外的な姿勢や内部統制、社内へのメッセージという観点でも大きな意味を持ちます。甘い対応をすれば、他の社員に誤った印象を与えることにもなりかねません。だからこそ、退職金の支給可否については、法的な基準と自社の企業理念の両面から総合的に判断し、必要であれば法的なサポートを受けながら対応を進めることが求められます。
損害賠償請求の可能性と回収に向けた現実的な対処法
横領が疑われる社員に対して、企業として当然検討すべきなのが損害賠償請求です。特に横領によって会社に直接的な金銭的損害が生じている場合、その全額について返還を求めることが原則となります。これは、過失による損害とは異なり、横領という「故意」の行為である以上、賠償範囲に限定がかかることは原則としてありません。
よくある誤解として、「従業員の損害は全額請求できないのではないか」というものがありますが、それは過失や軽度のミスに基づく損害の場合に限った話です。今回のように、意図的に金銭を持ち出した横領行為であれば、100%の損害額を請求することが法的にも認められます。よって、企業側としては毅然とした対応で、損害の全額返還を求めるべきです。
もっとも、法的に請求が可能であっても、実際に回収できるかどうかは別問題です。横領を行うような社員は、そもそも金銭的にだらしない、あるいは既に資金に困窮していることも多く、会社側の請求に応じる能力がないことも珍しくありません。また、被害額が多額にのぼる場合は、本人の資産では到底カバーできないケースもあります。
こうした現実を踏まえると、損害賠償請求を行う際には「返還約束書を取り付ける」「分割払いの合意を取る」といった現実的な対応も検討すべきです。さらに、社員に身元保証人がついている場合は、その保証人に対しても請求できる可能性があるため、契約書の確認と並行して請求の可否を検討する必要があります。
損害賠償請求は、単に金銭の問題にとどまらず、企業の姿勢を示す意味でも重要です。たとえ全額が回収できないとしても、一定の回収努力を行うことで「不正には毅然と対応する」という方針を内外に示すことができます。現実的な解決を図るためにも、損害の確定、請求方法の選択、保証人の確認などを含めた対応を、弁護士と連携して進めていくことが望まれます。
刑事告訴の検討と会社としての方針決定のあり方
横領という重大な不正行為に直面した企業にとって、刑事告訴を行うかどうかの判断は大きな分かれ道となります。被害の内容が明白であればあるほど、「このまま泣き寝入りするのか」「きちんと責任を問うべきではないか」という感情が強まるのは自然なことです。しかし、刑事告訴は単なる感情的対応ではなく、企業としての方針に基づいた戦略的な判断が求められます。
刑事告訴を行う目的には、犯罪行為に対するけじめをつける、再発防止のメッセージを内外に示すといった側面があります。特にコンプライアンスを重視する企業にとっては、「お金が戻ってきたから終わり」という姿勢はかえって不信を招くこともあるため、たとえ損害が回復されたとしても刑事的な責任を追及する姿勢を取ることが必要とされる場合もあります。
一方で、企業によっては、「被害額が回収できれば、それ以上の対応は求めない」といった柔軟な判断をすることもあります。小規模企業やリソースが限られた会社では、刑事手続きに関与する時間的・人的コストが重荷となることもあり、現実的な事情を優先せざるを得ないケースもあるでしょう。
重要なのは、刑事告訴を「すべきか・すべきでないか」という二択で考えるのではなく、「自社の方針や状況に即して、どう対応すべきか」を多面的に検討することです。そのためには、経営者自身が冷静に状況を整理し、法的・実務的な観点を踏まえながら判断することが不可欠です。
判断に迷う場合には、刑事告訴の実務に明るい弁護士と対話を重ね、アドバイスを受けることで、自社にとって最も適切な選択肢を見出すことが可能になります。法的知識を得るだけでなく、経営判断としてどう位置づけるべきかを整理するためにも、弁護士との「カウンセリング的な対話」は非常に有効です。
問題社員対応の判断に迷う企業への弁護士活用のすすめ
今回のような横領問題を含む問題社員(一般にモンスター社員とも言われている。)への対応は、一般的な労務管理と比較しても極めて難易度の高い対応が求められます。就業規則や法令を理解していても、実際の場面では多くの企業が判断に迷い、適切なタイミングを逃してしまうことも少なくありません。
こうしたケースでは、「正しい知識」を得ることと同時に、「自社にとってどの対応が最も現実的で、効果的か」という視点が欠かせません。その判断をサポートする存在として、弁護士を早期に活用することが非常に重要です。単に法的なアドバイスを受けるだけでなく、経営者の考えや社風、これまでの対応スタンスを丁寧に汲み取りながら、最適な方向性を一緒に整理していく「カウンセリング的な関わり」が求められる場面です。
たとえば「懲戒解雇に踏み切るべきか、退職を受け入れるべきか」「退職金を支払うべきか否か」「損害賠償や刑事告訴は本当に必要か」といった問題は、いずれも法的な基準だけで割り切れない側面があります。弁護士と丁寧に対話を重ねることで、経営者自身の考えを整理し、自社の価値観や方針に照らして最も納得のいく判断を導き出すことができます。
四谷麹町法律事務所では、問題社員への対応に関して、個別の注意指導の仕方や、懲戒処分の進め方、社員への対応方法について具体的なサポートを行っています。さらに、状況によっては企業側代理人として、問題社員や相手の代理人弁護士との交渉も行っています。
訴訟や労働審判になる前の段階から適切な対応を行うことで、企業側の負担を軽減し、トラブルの早期解決が可能となります。問題社員の対応でお悩みの際は、会社側専門の経験豊富な四谷麹町法律事務所にぜひご相談ください。