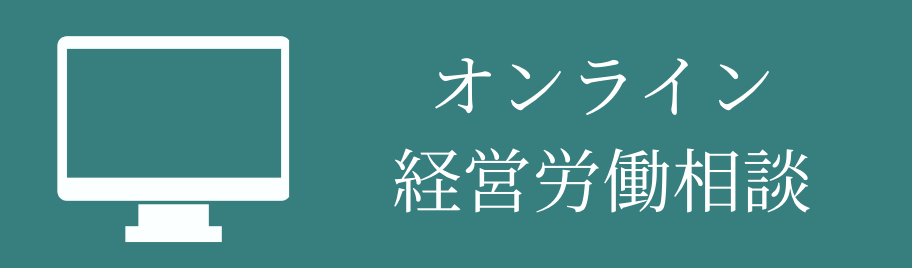「残業の必要がないのに帰らない社員」への対処法とは?マネジメントと法的対応の実務ポイント

目次
動画解説
残業の必要がないのに帰らない社員が引き起こす企業内の不公平とリスク
業務上の必要がないにもかかわらず、なかなか退社しようとせず、残業代を請求する社員がいると、企業内ではさまざまな問題が生じます。まず明らかに発生するのは、他の社員との不公平感です。
例えば、生産性高く仕事を早く終え、定時で退社した社員は残業代が発生しません。一方で、業務の効率を上げず、時間をかけてだらだら働いた社員が残業代を得るとなれば、その差は収入に直結します。こうした状況を放置すれば、誠実に働く社員の士気が下がり、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼすことになるでしょう。
経営上もこのような状況は非効率的であり、健全な企業運営を妨げる要因となりかねません。問題のある社員に対して適切な対応を行わなければ、全体の労務管理に歪みが生じ、やがては組織全体の崩壊にもつながる危険性があります。
職場秩序の乱れとマネジメント不全の深刻な影響
残業の必要がないにもかかわらず退社しない社員の存在を放置することは、マネジメントの機能不全を意味します。もし「早く帰ってほしい」と思っていながらそれを明確に伝えず、だらだらとした残業を容認しているのであれば、それは管理職が職責を果たしていないということになります。
残業が正当な理由に基づき、上司や会社の承認のもとで行われるのであれば、それは健全な労務管理です。しかし、実態としては「無理するなよ」「早く帰りなよ」といった優しい声かけのみで終わっているケースが多く見られます。これでは本気で帰ってほしいという意思が伝わらず、問題社員を止めることができません。
マネジメントとは「結果を出すこと」が求められる仕事です。単に言葉で注意するだけでなく、現実に退社させるまで行動することが求められます。このような管理ができていない場合、管理職の適格性そのものが問われる問題でもあります。
長時間労働が企業に与える健康リスクと法的責任
社員が長時間にわたり会社にとどまり、残業らしき行動を続けていた場合、たとえ業務密度が低くても、健康リスクを軽視することはできません。長時間労働は心身に大きな負荷を与えるものであり、企業には安全配慮義務が課せられています。
「だらだら働いているだけだから問題ない」と楽観視することはできません。実際に健康を害した場合、「長時間会社にいたことを会社は知っていたのではないか」と問われ、過失が認定されやすくなります。また、精神疾患による労災認定の際にも、長時間労働が一因とされるケースは多く、リスクは決して小さくありません。
このような健康リスクを軽減するためにも、必要のない残業を許容しない体制を整え、社員の労働時間を適切に管理することが、企業の重要な責務となります。
「帰ってくれない社員」はマネジメントの問題である
会社と社員は労働契約によって結ばれており、その内容は「会社が業務を指示し、社員が従う」というものです。残業の要否を決定する権限はあくまで会社側にあります。つまり、社員が勝手に残業すること自体、契約の原則から逸脱していると言えます。
とはいえ、現場の実務を管理する上司や管理職がその権限を行使しない限り、社員の行動を止めることはできません。「好きに残業していいよ」と裁量を与えたのであれば、それは管理職自身の判断です。そして、その裁量が不適切だと判断したならば、権限を見直し、必要に応じて制限すべきです。
「帰るように言ってるけど、なかなか帰ってくれない」と嘆く経営者は多いですが、そこにあるのは「伝え方の甘さ」であり、本気で帰す覚悟がないことが問題です。実際に帰らせる行動にまで至らなければ、マネジメントとは呼べません。
社長・上司・管理職が取るべき具体的な対応策とは
部下がなかなか帰らない場合、まずは残業が本当に必要かを確認することが重要です。具体的には、翌日では対応できない理由があるのか、業務に支障が出るのかなどを問いかけ、部下の説明を聞いてください。そのうえで、合理的な理由があると判断した場合は、正当な手続きで残業を認め、残業代も支払う必要があります。
一方で、必要性がないと判断した場合には、はっきりと「帰ってください」と命じる必要があります。「無理しないように」「早く帰れよ」といった曖昧な表現は避け、マネジメントとしての責任を持って行動してください。
さらに、実際に帰るよう促した際には、オフィスの仕事スペースから物理的に出るところまで確認することで、実効性のある指示を徹底させることができます。部下がそれでも従わない場合には、単なる注意にとどめず、必要に応じて「これは命令である」と伝える段階に進まなければなりません。
このように、残業を管理するには「明確な判断」「実際の行動」「結果を出すこと」が必要です。管理職としての本来の役割を果たすことが、問題社員の行動を抑止し、企業の健全な運営を支える基盤となります。
残業代請求への備え:支払い義務の有無を分ける法律的ポイント
では、実際に「必要がないはずの残業」をされた場合、その分の残業代を会社は支払う必要があるのでしょうか。ここで重要になるのが、労働基準法に基づく時間外労働の取り扱いです。
法律上、1日8時間・週40時間を超える労働には、割増賃金の支払いが義務付けられています(労基法第37条)。これは当事者間の合意や、「残業代いらない」といった本人の意向によっても無効化されません。よって、法定労働時間を超えていた場合には、原則として残業代の支払いが求められます。
一方、所定労働時間と法定労働時間の間(たとえば7時間30分と8時間の間)については、会社ごとの就業規則や労働契約に基づいて支払義務の有無が判断されます。契約や規則が不明確な場合、解釈に基づく判断となり、トラブルの種になりやすいため、あらかじめ明記しておくことが極めて重要です。
黙示の残業命令と判断されるリスクと回避のための注意点
会社が明示的に残業を命じていない場合でも、社員が残業を続け、それを上司が知りながら止めなかった場合、「黙示の残業命令」があったと評価されることがあります。
たとえば、タイムカードや入退館記録で長時間の在社が確認できるのに、会社が何の対応も取っていなかった場合には、「残業を容認していた」と受け取られかねません。これが認定されると、残業代支払義務が発生し、さらには長時間労働による健康被害が出た際には、安全配慮義務違反とされるリスクも高まります。
このような事態を防ぐには、長時間の在社が判明した時点で面談を行い、業務の必要性の有無を確認したうえで、適切なマネジメントを行うことが不可欠です。放置することなく、早期に対応することが会社を守る鍵となります。
「だらだら残業」対策制度を導入する際の留意点
マネジメントの重要性は理解しているものの、「現場でうまく運用できない」「人材が足りない」という企業も少なくありません。そうした場合に多く導入されるのが、「事前許可制」や「固定残業代」といった制度です。
まず事前許可制は、残業を行う前に上司の許可を得る仕組みですが、これはルールの運用がすべてです。許可を得ずに残業を行った社員に対して注意や指導を行わずに放置した場合、結局は黙示の残業命令と評価されてしまいます。
ルールを形骸化させないためには、許可制を導入したならば、違反があった際にしっかりと指導できる風土づくりと、管理職への意識徹底が必要です。制度をつくること以上に、制度を「運用できるかどうか」が、残業代請求リスクを左右します。
固定残業代制度の落とし穴と導入のリスク
固定残業代制度は、一定時間分の残業代をあらかじめ月給に含めて支払う制度ですが、この制度が正しく機能するためには「判別可能性」と「対価性」という2つの法的要件を満たす必要があります。
判別可能性とは、固定残業代が基本給などの他の賃金部分と明確に区別されていること。対価性とは、固定残業代が時間外労働の対価として支払われていることが明確であることを指します。これらが満たされていないと、固定残業代として認められず、実際の残業に応じた残業代を追加で支払う必要が生じるリスクがあります。
また、固定残業代があることで、管理職が「多少残業してもどうせ給料は変わらない」と管理を怠るようになれば、結果的に長時間労働の温床となりかねません。制度導入時には、契約書や就業規則への明記はもちろん、運用管理にも細心の注意を払うべきです。
経営者が果たすべきマネジメントの責任と対応の最終手段
最終的に重要なのは、経営者・管理職のマネジメント力です。部下が退社しない状況に対し、「言ったけど帰らない」と放置するのではなく、実際に帰らせるための行動が求められます。説得が通じない場合は、明確に「これは命令である」と伝え、それでも従わなければ、書面での残業禁止命令や懲戒処分の検討も必要となります。
ここまでの段階に達した場合は、問題社員(一般にモンスター社員とも言われている)とのトラブル対応として、法的対応が必要になるケースもあります。放置せず、早めの対応が企業を守る第一歩です。
四谷麹町法律事務所では、問題社員への対応に関して、個別の注意指導の仕方や、懲戒処分の進め方、社員への対応方法について具体的なサポートを行っています。さらに、状況によっては企業側代理人として、問題社員や、相手の代理人弁護士との交渉も行っています。
訴訟や労働審判になる前の段階から適切な対応を行うことで、企業側の負担を軽減し、トラブルの早期解決が可能となります。問題社員の対応でお悩みの際は、会社側専門の経験豊富な四谷麹町法律事務所にぜひご相談ください。