2025.06.16
「就労可能」の診断書で復職したのに働けない社員への対応法|精神疾患の場合のマネジメントと法的対処
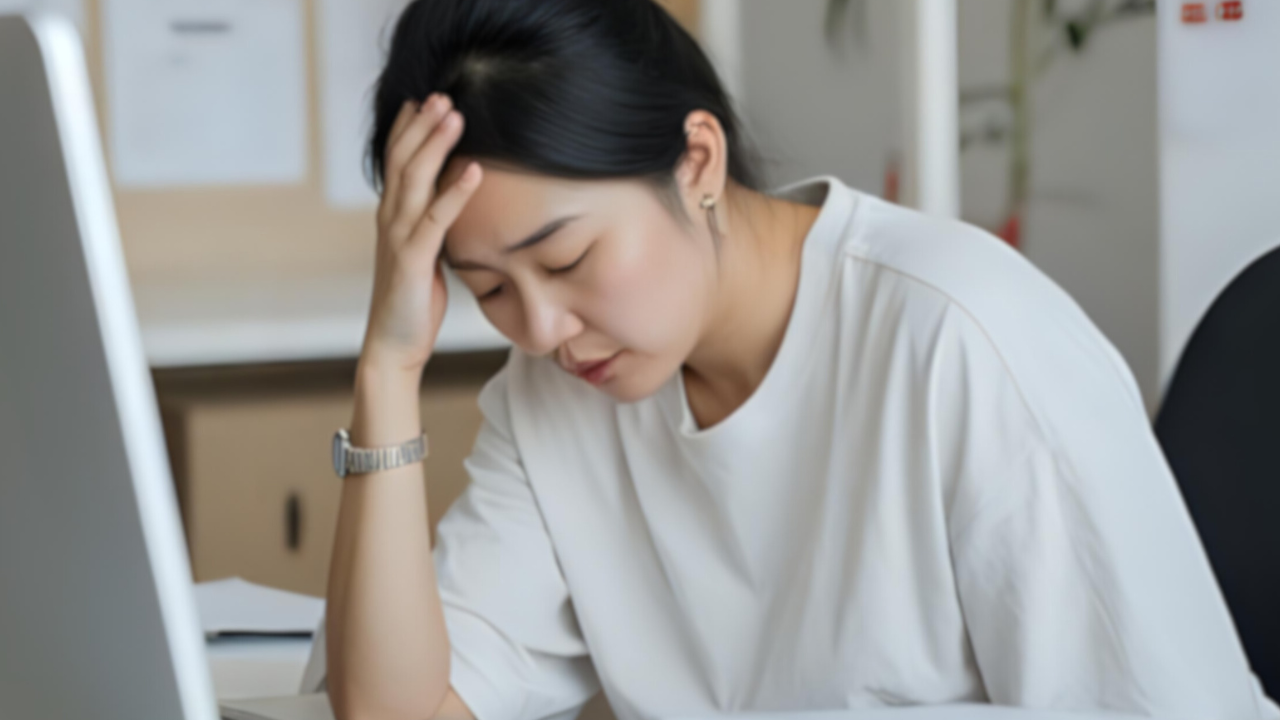
目次
動画解説
主治医の「就労可能」診断書に安易に依存してはいけない理由
社員が「就労可能」と記載された主治医の診断書を提出してきた場合、経営者の多くは「医師が働けると言っているなら復職させよう」と考えるのが自然でしょう。しかし、特に精神疾患の場合はそう単純に判断できるものではありません。
精神疾患の特性として、表面的には日常生活を送れていても、職場というストレス環境下での業務遂行能力までは回復していないケースが多く見受けられます。そのため、医師が出す「就労可能」の診断書であっても、必ずしも企業で求められる労働が可能な状態を意味しているとは限りません。
実際、復職後に全く仕事にならず、なぜ「就労可能」と診断されたのか疑問に感じるようなケースも多数存在します。経営者は医師の診断書を尊重しつつも、それに過度に依存せず、実態に即した慎重な対応が求められます。
仕事ができない場合に企業が考慮すべき2つの義務
復職した社員が明らかに仕事ができない場合、企業側が直面する法的・実務的責任は二つあります。それが「安全配慮義務」と「不完全な労務提供の受領拒否権」です。
まず、安全配慮義務とは、会社が社員の健康と安全に配慮する責任です。体調が回復していない社員を無理に働かせることで、さらに症状が悪化すれば、会社側に責任が問われる可能性があります。これは特に精神疾患において重大な問題です。
次に、労働契約は「労働の提供に対して報酬を支払う」という関係に基づいています。したがって、著しく不完全な労務提供に対しては、企業はそれを受け入れる義務を負いません。つまり、社員が就業できる状態ではないと判断される場合、会社は「欠勤」として扱い、勤務を控えさせる正当な権利があります。
欠勤と休職を正しく区別し、休職命令書で対応を明確に
実際に社員が働けない状態であれば、まずは欠勤扱いとすることが一般的です。年次有給休暇を使う場合を除けば、基本的には無給の欠勤処理となります。そして、一定期間欠勤が続いた場合、休職制度のある企業では「休職」に移行することになります。
ここで重要なのが、「休職命令書」の発行です。休職期間には、満了後に退職となる重大な結果が伴うため、開始日を明確にすることが求められます。特に就業規則で「休職命令をもって休職開始とする」と定めている企業では、命令を出さない限り休職が始まりません。
適切な命令書を発行し、休職の開始日を正式に記録することは、後々のトラブル防止の観点からも非常に重要です。緩やかな運用をしている企業でない限り、必ず文書での対応を行うようにしましょう。
出社しているが仕事ができない社員への実務対応
復職後、出社はしているものの、業務が全く遂行できない社員がいた場合、会社としての対応は非常に難しい判断を迫られます。このような場合、「出勤しているのだから給与を支払わなければならないのではないか」と悩む経営者も多いでしょう。
しかし、出勤していても、実質的に労務提供がなされていなければ、労働契約上の義務は履行されていないと見なすことができます。このようなケースでは、会社は安全配慮義務の観点からも、その社員を欠勤扱いとし、必要であれば早退や自宅待機を命じるべきです。
また、「頑張ります」と言って無理をする社員に働かせ続けることは、体調をさらに悪化させるリスクを伴います。企業としても本人の健康を守る姿勢が問われますので、明確な対応を取るべきです。
給料支払いの判断基準とリスクへの備え
仕事ができていない社員に対して給与を支払うかどうかの判断は、労働実態に基づいて慎重に行う必要があります。実際に業務が遂行できていないのであれば、給与を支払う義務はないとされるのが原則です。
ただし、給与の未払いがトラブルに発展することもあり得るため、対応にあたっては客観的な記録の整備が欠かせません。社員の業務実績、日報、面談記録などを残し、どのような働き方であったのかを明確にしておくことが重要です。
さらに、産業医による面談や主治医への再確認など、医療的な側面からも働けるかどうかを判断する手続きを踏むことで、会社の判断の正当性を裏付けることができます。リスクをできる限り回避するには、こうした多角的な情報収集と記録管理がカギとなります。
再復職の申し出を受けた際の慎重な判断の必要性
一度復職させたものの、実際には働けなかったという過去の経緯がある場合、次に「復職したい」と申し出があった際は、通常以上に慎重な判断が求められます。同じ失敗を繰り返すことは、会社経営にとって非常に不合理ですし、本人にとっても再び体調を崩すリスクを高めることになります。
復職の可否については、医師の診断書だけで決めず、会社が主体的に状況を見極めることが必要です。復職の判断には業務内容や職場環境の負荷など、主治医が把握していない要素も多く含まれます。したがって、診断書の記載をそのまま鵜呑みにするのではなく、職場での就労が実際に可能かどうかを、実務レベルで慎重に判断すべきです。
主治医の診断書は判断材料の一つに過ぎない
「就労可能」と記載された主治医の診断書は、企業として無視すべきものではありませんが、復職可否を決定づける絶対的な証拠でもありません。精神疾患に関する診断書は、しばしば日常生活における回復状況を基に判断されており、職場での実際の業務遂行能力まで考慮されていないことがあります。
また、主治医は職場の仕事内容や負荷を詳しく把握していないケースも多く、さらには患者や家族の希望を汲んで診断内容を記載することもあり得ます。例えば、「休職期間が終わる前に復職できないと解雇される」といった不安を抱える患者からの相談に応じる形で、やや前のめりな診断がなされることも考えられます。
そのため、企業としては主治医の診断書を参考にしつつ、最終判断は産業医の意見や会社での勤務実績、業務への適応状況など多角的な情報に基づいて行う必要があります。
産業医・指定医師の活用と「試し出社」の実務的意義
会社に産業医がいる場合は、必ず産業医面談を実施し、復職の可否について客観的な意見を得るようにしましょう。必要に応じて、産業医から主治医への情報提供依頼や、社員の同意を得た上での主治医との面談なども検討することが可能です。
また、会社が指定する医師による診察を義務付けることも、合理的かつリスク回避的な対応として有効です。このようなプロセスを経ることで、復職が可能かどうかについて、より正確な判断が可能となります。
さらに、「試し出社」などの制度を用いることで、いきなりフルタイムの復職をさせるのではなく、段階的に様子を見ながら判断することもできます。短時間勤務や軽作業から始めて、実務能力や健康状態を確認しつつ本格的な復職につなげるという方法は、本人にとっても企業にとっても現実的で安全な選択肢となります。
働けない場合の原則対応と例外的な柔軟対応
企業が「この社員は現時点で労働契約で予定されている程度の労務提供ができない」と判断した場合は、原則として欠勤扱いとし、必要に応じて休職命令を出して正式に休職に移行させる対応が必要です。
一方で、症状がある程度改善しており、「3か月程度でフルタイム勤務に復帰できる見込みがある」と判断できる場合などは、例外的に柔軟な対応を取ることもあります。たとえば、当面は就業制限を設けつつ、段階的に通常勤務へ戻すという方針もあり得ます。
ただし、柔軟対応はあくまで状況次第であり、その見込みがなければ就業継続は難しくなります。休職期間中であればそのまま継続、欠勤状態であれば一定期間経過後に休職命令、さらに休職期間満了後には退職(普通解雇等)の対応に進むことが原則です。ここでも会社のルールに従った適正な運用が求められます。
経営者がとるべき対応と判断のための相談体制の重要
経営者としては、「主治医の診断書があるから働けるはずだ」と考えるのではなく、社員の健康と職場の健全性を両立させる観点から慎重に対応することが求められます。不完全な労務提供を無条件で受け入れる義務はなく、また社員の健康を守る義務も企業側にあるということを忘れてはいけません。
曖昧な対応は、結果として社員の体調悪化や企業の責任問題に発展する可能性があるため、明確な対応が必要です。判断が難しい場合や、法的リスクが懸念される場合には、早めに弁護士へ相談することを強くおすすめします。
四谷麹町法律事務所では、復職問題に関して主治医の診断書の取り扱い方、産業医との連携方法、復職判断の手順、さらには対応方針の策定まで、企業の立場に立ったサポートを行っています。就労可否の判断や、労働契約上の措置に悩んだ際は、ぜひお気軽にご相談ください。












