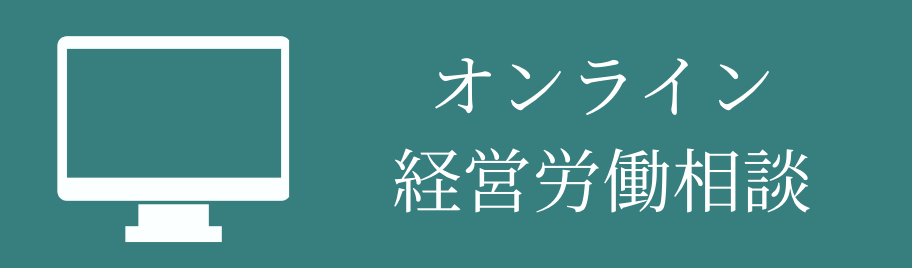転勤・職種変更を拒否する社員への対応方法|法的要件と実務のリスク管理

目次
動画解説
配転に応じない社員が増加する背景
近年、転勤や担当業務の変更といった「配転」に応じない社員が増えています。企業が多くの社員を雇用し、会社全体の労働力を有効に活用していくためには、どの仕事を誰に担当してもらうか、どの勤務地で働いてもらうかを会社が決定し、それに従って働いてもらうことが基本となります。特に長期雇用を前提とする場合には、今いる社員をうまくやりくりしながら、会社全体の必要な労働力を賄っていく必要があります。その手段として「配転」は非常に有効な制度です。
しかしながら、時代の変化とともに、転勤や職務変更に抵抗を示す社員が増加しています。家庭の事情などから「引っ越しはしたくない」「今の地域で暮らし続けたい」という希望を持つ社員が増えているほか、「自分の希望する業務だけをやりたい」「他の職種はやりたくない」といった働き方の価値観も広がっています。
こうした背景には、家庭環境や社会の変化があります。たとえば共働き世帯の増加により、配偶者も正社員として働いているケースが多くなり、転勤を命じられた側が単身赴任を余儀なくされる、あるいは配偶者が退職を検討しなければならないといった問題が生じやすくなっています。また、育児や介護を家庭内で分担することが一般的となり、家族の誰かが転勤することで生活全体に大きな支障が出るケースも増えています。
さらに、会社に一生勤め続けるという前提が崩れたことで、社員の側も「自分のキャリアを自分でコントロールしたい」「他社でも通用するスキルを身につけたい」といった意識が強くなっています。そのため、会社からの命令に一方的に従うよりも、自分の生活やキャリア設計を優先する傾向が見られます。
一方で、企業側としては人手不足が続く中、社員に辞められてしまうと経営上の打撃が大きく、簡単に「命令に従わないなら辞めてもらえばいい」とも言えません。したがって、今後の配転問題を考える際には、単に「法的に有効かどうか」「裁判に勝てるかどうか」といった観点だけではなく、社員が納得し、生き生きと働ける環境をどのように整えるかという視点が不可欠です。
時代の変化に対応し、自社らしい対応方針をしっかり構築できているかどうか――それこそが、現代の企業経営者に求められる重要な課題と言えるでしょう。
配転命令を出すために必要な2つの条件とは
配転命令を有効に行うためには、まず基本となる2つの要件を確認しておく必要があります。これを誤ると、命令が無効と判断されたり、後のトラブルに発展したりするおそれがあります。ポイントは「配転命令権限があること」と「権利の濫用に当たらないこと」の2つです。
まず1つ目の「配転命令権限」とは、契約上、社員に対して別の職務を命じたり、別の勤務地で働かせたりする権限のことです。多くの場合、正社員であればこの権限は会社側に認められています。正社員の労働契約では、勤務地や職種を限定していないケースがほとんどであり、原則として会社が必要に応じて人事異動を行うことが可能です。そのため、正社員に関しては配転命令権限自体が存在するケースが大半です。
ただし、例外もあります。たとえば、労働契約の中で「この勤務地のみで勤務する」「この業務だけを担当する」といった勤務地限定・職種限定の合意がある場合には、会社が一方的に他の勤務地や他の職種への異動を命じることはできません。形式上「正社員」であっても、こうした合意があれば、配転命令の権限は制限されることになります。したがって、契約内容を確認することが非常に重要です。
また、パートやアルバイトの場合は、正社員以上に勤務エリアや担当業務が限定されている契約が多いため、配転命令権限がそもそも存在しない場合もあります。このため、非正規社員に対しては特に慎重な確認が必要です。
さらに、2024年4月以降、労働条件の明示義務が改正され、労働契約を結ぶ際には「就業場所や業務の変更の範囲」まで明示することが義務づけられました。従来は、初期の勤務地や業務内容を示せばよいとされていましたが、今後は「どの範囲まで変更があり得るのか」も明確に示さなければなりません。企業としては、この法改正に対応して労働条件通知書などを見直しておくことが求められます。
そして2つ目の要件が「権利の濫用に当たらないこと」です。会社に配転命令の権限があるからといって、どのような命令でも自由に出してよいわけではありません。濫用的な命令、すなわち業務上の必要性がない異動や、不当な目的に基づく配転などは無効と判断されます。
この点については、後の項目で詳しく触れますが、労働問題の分野では「権限があるかどうか」だけではなく、「その使い方が適切であったかどうか」が非常に重視されます。解雇や懲戒処分と同じく、配転命令においても「濫用でないこと」を丁寧に確認することが、企業としての重要なリスク管理になるのです。
配転命令が「権利の濫用」と判断されるケース
配転命令を出す際、たとえ契約上の権限があったとしても、その行使が「権利の濫用」に当たると判断されれば、命令は無効になります。労働契約上の権利があっても、それを不適切に使えば認められないというのが、労働法の基本的な考え方です。特に雇用関係においては、労働者と使用者の間に力の差があることから、裁判所は労働者を保護する方向で判断する傾向があります。
配転命令の濫用性を判断する際には、大きく3つの要素が考慮されます。
第一に「業務上の必要性があるかどうか」です。配転には当然会社の事情が伴うわけですが、その異動が本当に業務上必要だったのかが問われます。とはいえ、この必要性のハードル自体はそれほど高くありません。たとえば、ローテーション人事や社員育成といった理由でも、一定の業務上の必要性は認められる傾向にあります。ただし、必要性がしっかり説明できるよう準備しておくことは重要です。それにより、他の判断要素――たとえば「不当な目的ではない」「不利益も通常の範囲内」といった主張の説得力が増すからです。
第二に「不当な動機・目的があったかどうか」です。典型例としては、退職勧奨を断った社員に対し、嫌がらせ目的で配転命令を出したようなケースです。このようなケースでは、命令の背景に問題があると判断され、無効とされることがあります。たとえば、退職を促した直後に急に遠方の勤務地への異動を命じたような場合、「辞めさせるための配転ではないか」と疑われるリスクがあります。過去にそのような配転がなかった場合や、本人に適性がない部署へ突然異動させるといった事情も、「不当な動機」と受け取られやすいです。
第三に「労働者に著しく大きな不利益を与えるものではないか」です。配転によって一定の不利益が生じるのは当然とされますが、その程度が「通常甘受すべき範囲」を超えている場合には、配転命令が無効となる可能性があります。たとえば、転居を伴う転勤により家庭が大きな影響を受ける、育児や介護が困難になるといった場合には、注意が必要です。最近では、こうした家庭事情への配慮を怠ることが、法的リスクに直結することもあります。
この3つの要素――業務上の必要性、不当な目的の有無、不利益の大きさ――は、最高裁の「東亜ペイント事件」で示された基準をもとに判断されています。この判例は昭和時代のものですが、今日でもこの枠組みは有効とされており、現在の労働環境に応じて個別具体的に適用されています。
企業としては、配転命令を出す際にこれらの要素を丁寧に検討し、命令の妥当性を裏付ける社内記録や説明をきちんと整えておくことが重要です。濫用に該当しないよう、法的な要件だけでなく、社員個人の事情にも十分に配慮した運用が求められています。
転勤命令と家族事情への配慮の必要性
現在、転勤を命じた際に「嫌です」「応じたくありません」と明確に拒否する社員が増えている背景には、家庭事情の変化が大きく関わっています。特に、配偶者も正社員として働いている共働き家庭が一般的になっている現代においては、転勤がもたらす影響は非常に大きなものとなります。
たとえば、かつては夫が正社員で働き、妻が専業主婦という世帯も少なくありませんでしたが、現在では夫婦ともに正社員という家庭が当たり前になりつつあります。そのため、夫の転勤によって家族で引っ越すとなれば、妻が正社員を辞めなければならないという選択を迫られるケースもあります。こうした状況では、夫が単身赴任を選ばざるを得ない場合も多く、家庭全体に大きな負担をかけることになります。
さらに問題なのは、単身赴任によって家庭での育児や介護に支障が出るケースです。共働き家庭では育児や介護を夫婦で分担していることが多く、一方の親が不在になると、残された配偶者や家族に過度な負担がかかってしまいます。かつてのように「家のことは妻に任せて、夫は仕事に専念すればよい」という時代ではなくなっており、夫も育児や介護の担い手として重要な役割を果たしています。こうした家庭事情を無視して一方的に転勤を命じることは、大きなトラブルの原因となりかねません。
このような背景を踏まえ、育児・介護休業法26条では、「就業場所の変更を伴う配置転換をしようとする場合には、育児や介護に支障が生じないように配慮しなければならない」と明記されています。この配慮義務は単なる努力義務ではなく、事業主に課された法的義務です。さらに、こうした事情を会社に相談したことを理由に、解雇や不利益な取り扱いをすることも法律で禁止されています。
また、家族事情以外にも、社会活動や地域での交友関係を大切にする社員が増えており、「転勤すると自分らしい生活が送れなくなる」という理由で異動を拒むケースもあります。こうした価値観の多様化も、企業としては無視できない要素です。
時代が変わり、社員一人ひとりの背景が複雑化している今、転勤命令に対して従来通りの画一的な対応を行うことは、法的リスクだけでなく、社員の離職という重大な経営リスクにもつながります。法的な要件を満たしていたとしても、社員の生活への影響をしっかりと見極め、慎重な判断と十分な配慮が必要となる時代になっているのです。
担当業務の変更(職種変更)と社員の意識変化
転勤と並んで企業が直面する課題の一つが、担当業務の変更、いわゆる「職種変更」に応じない社員への対応です。最近では「自分の仕事は自分で決めたい」と考える社員が増えており、こうした意識の変化は無視できないものになっています。背景には、経済環境や雇用慣行の変化、そして社員一人ひとりのキャリアに対する考え方の変化があります。
かつては「定年まで雇ってくれる会社に従って働く」という考え方が一般的でした。しかし、近年は企業の業績悪化によるリストラ、早期退職制度の導入などが進み、「会社が一生面倒を見てくれる時代ではない」という現実を、多くの社員が実感しています。その結果、「会社に依存せず、他社でも通用するスキルを身につけておきたい」と考えるようになり、自分の適性に合った職種、これまでの経験を活かせる業務にこだわる傾向が強まっているのです。
たとえば、営業職として長年スキルを積んできた社員が、急に未経験の製造部門へ異動を命じられた場合、単に業務が変わるだけでなく、自身のキャリア形成にも大きな影響を及ぼすと考えるでしょう。「これまで培ってきたスキルを活かせない」「転職市場でも評価されなくなる」といった不安を抱えれば、異動命令に反発するのも無理はありません。
企業としては、こうした社員の意識変化を踏まえた上で、職種変更を命じる場合には、より丁寧な対応が求められます。もちろん、正社員であれば契約上、職種変更の命令権限があるケースが大半ですが、それでも「辞めさせるために適性のない業務を押しつけたのではないか」と疑われるような対応は、法的にも無効と判断されるリスクがあります。
逆に言えば、適法な範囲での職種変更であり、明確な業務上の必要性があり、不当な目的や過度な不利益がない限りは、裁判においても企業側が勝つ可能性は高いといえます。さらに、職種変更命令に応じなかったことを理由に解雇することも、一定の条件を満たせば認められる傾向にあります。
ただし、ここで企業が本当に注意すべきなのは、「社員に辞められてしまうリスク」です。転職がしやすい売り手市場の中で、無理な職種変更を強行すれば、社員が退職を選択する可能性が高まります。社員にとっては、「不本意な異動を受け入れて消耗するより、自分の希望に合った職場へ転職するほうがよい」と考えるのは、自然な流れです。
職種変更についても、単に法的に命令できるかどうかだけではなく、社員の意識やキャリア観を踏まえた柔軟な対応が求められる時代となっています。企業が社員を活かすための戦略として、職種変更をどう位置づけ、どう進めるか。人事政策における重要な検討課題といえるでしょう。
配転命令や職種変更命令をめぐる法的リスクと現実
配転命令や職種変更命令をめぐって、企業側が法的に裁判で勝てるかどうかは、これまでの判例から見ても比較的高い可能性があると言えます。命令自体が有効であると判断されることも多く、違反したことを理由とする解雇も認められやすい傾向があります。ただし、その前提には、命令に「権限があること」と「濫用でないこと」がしっかりと満たされている必要があります。
とはいえ、実務上のリスクは必ずしも裁判の勝ち負けだけでは測れません。最も注意すべきリスクは、「社員に辞められてしまうこと」です。企業がいくら法的に正当な配転命令や職種変更命令を出したとしても、それによって貴重な戦力が退職を選ぶのであれば、結果的に企業にとって大きな損失となります。
特に現代では、人手不足が深刻化し、転職市場も活況を呈しています。売り手市場のなか、社員が転職を選ぶハードルはかつてよりもはるかに低くなっており、「異動が嫌だから辞める」という選択をする社員も増えています。これは、かつてのように終身雇用への信頼が強かった時代とは明らかに異なり、社員が会社に全幅の忠誠を誓うような時代ではなくなってきていることを意味します。
また、社員一人ひとりが自分の人生やキャリア設計を重視し、「会社のために犠牲になる」という考え方を持たないことも増えています。転勤によって育児や介護に支障が出る、自分のキャリアから外れる仕事を命じられるといった状況になれば、「法的に有効かどうか」以前に「この会社で働き続ける価値があるのか」と判断されかねません。
企業が考えるべきは、「裁判で勝てるか」ではなく、「命令を出した結果、会社にとって本当にプラスになるのか」という視点です。たとえ裁判に勝てたとしても、その過程で社員との信頼関係を損ない、人材流出が進んでしまっては本末転倒です。法律論だけではなく、経営判断としてのリスク評価がますます重要になってきているのです。
こうした時代においては、法的要件を満たすだけでなく、社員が納得し、自社にとどまって活躍し続けてくれる環境をどう整えるか――その視点が経営者や人事担当者にとって不可欠です。
実際の対応には個別事情の把握が不可欠
配転や職種変更に関して、時代が変わり社員一人ひとりの事情も多様化しているなかで、従来のような画一的な対応ではもはや通用しなくなってきています。全社員に同じような異動命令を出すのではなく、個別事情を踏まえた丁寧な対応が必要とされています。
特に転勤や職種変更を打診した際に、「嫌です」「できません」といった反応があった場合、企業側としてはその理由を慎重に聴取することが求められます。「どうして異動に応じられないのか」「家庭の事情なのか」「健康上の理由なのか」など、その背景を具体的に把握することで、適切な判断や配慮につなげることが可能になります。
大規模な企業では、事前に社員の希望をアンケート調査で把握しておくことも一般的です。たとえば、「転勤の可否」「希望勤務地」「興味のある業務内容」などを定期的に調査しておくことで、異動時のトラブルを未然に防ぐことができます。このような取り組みは、社員の意見を尊重する姿勢としても評価され、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。
一方で、事前の希望調査だけでは対応しきれない部分もあります。実際に異動を検討する際には、候補者との個別面談を行い、本人の意向を確認し、その理由を具体的に聴き取る必要があります。場合によっては、家族構成や介護・育児の状況、通院の必要性など、プライベートに関わる情報まで踏み込むことも出てきます。その際には、プライバシーへの配慮を欠かさず、信頼関係を前提とした対話が不可欠です。
また、本人の申し出だけでなく、それを裏付ける資料の提出を求めることで、対応の公平性や客観性を担保することができます。たとえば、育児や介護に関する事情であれば、保育園の証明書や介護認定の情報などを提出してもらうことで、会社としての判断材料がより明確になります。
このように、配転や職種変更に関しては、まずは個別の現状を正確に把握することが出発点です。その上で、業務上の必要性とのバランスをどう取るか、配慮すべき事情がどこまであるのか、具体的に検討していく必要があります。精度の高い現状把握なくして、適切な判断はできません。経営者や人事担当者には、こうした「見えにくいリスク」に対してこそ、丁寧に向き合う姿勢が求められています。
命令を出す前に必要な比較検討と社内判断
配転や職種変更の命令を出す前に、企業として必ず行うべきなのが、「業務上の必要性」と「社員の要望・事情」の比較検討です。命令が法的に有効かどうかを確認することは前提として重要ですが、それだけで命令を出すのは不十分です。実際には、法的に有効であっても社員が納得しなければ、モチベーションの低下や退職といった経営上のリスクが発生します。
まず、命令を出す前には、対象社員との面談を通じて事情の聴取を行います。「なぜ異動が必要なのか」「どのような負担が生じるのか」を把握したうえで、業務上の必要性と比較し、どちらの事情が優先されるべきかを検討しなければなりません。
たとえば、会社としてはある部署にどうしても人員を補充しなければ業務が回らないといった切実な事情がある一方で、社員側に家庭の介護や育児などやむを得ない事情があるとすれば、その配転が本当に必要か、他に代替手段はないかを慎重に見極める必要があります。
判断にあたっては、次のような視点が役立ちます。まず、自社にとって配転がどれだけの経営的必要性を持つか。給与水準や雇用の安定性、企業ブランドなど、自社の魅力を踏まえた上で、社員がどの程度辞めにくい環境にあるのかも検討要素となります。たとえば、「当社は給与が高く、ブランド力もあるため、多少の異動なら社員は受け入れるだろう」といった見通しがある一方で、「最近若手の離職が相次いでいる」などの傾向がある場合は、命令の出し方に注意を要します。
さらに、社員本人の性格やこれまでの勤務態度、価値観なども判断材料になります。たとえば、「周囲との協調を大事にするタイプ」「家庭第一の志向が強い」など、社員の傾向を踏まえて判断すれば、命令を出した場合の反応もある程度予測できます。
このように、配転や職種変更命令は単なる法律判断ではなく、経営的な意思決定でもあります。「命令を出せるかどうか」ではなく、「命令を出すことで会社にとって本当にプラスになるか」を見極める姿勢が求められます。そのためにも、的確な判断を下すには、事案ごとの事情を丁寧に調査し、必要であればコンサルティングが可能な弁護士など専門家と連携して対応していくことが重要です。
法的判断だけではなく、経営判断としての配転を
配転や職種変更に関する問題において、企業が考慮すべきは「裁判で勝てるかどうか」だけではありません。たとえ法的に有効な命令であっても、それによって社員が不満を抱き、モチベーションを失ったり、最悪の場合は退職してしまったりすれば、企業にとっては大きな損失となります。特に現在のような人材不足の時代においては、優秀な社員の離職は深刻な打撃となり得ます。
これまでの労働法の運用上、配転命令や職種変更命令は、権限があり、かつ権利の濫用に当たらなければ、有効と判断されるケースが多くありました。裁判でも企業が勝つことは少なくありません。しかし、裁判で勝つというのは、多くの場合「最終的な後始末」に過ぎません。訴訟になった時点で、企業としてはすでに大きな人的・時間的・ reputational コストを負っている可能性が高く、それ自体が企業の損害にもなりかねないのです。
今後は、法的な対応だけではなく、「どうすれば社員が納得し、生き生きと働けるか」「どうすれば辞められずに済むか」といった視点が、経営判断としてますます重要になります。配転は単なる人事異動ではなく、社員一人ひとりのキャリアや人生に大きな影響を与えるものです。それを一方的に進めてしまえば、会社への信頼や職場環境に悪影響を与えるおそれがあります。
また、配転は「タレントマネジメント」の一環でもあります。社員の適性を見極め、最適な部署で最大限のパフォーマンスを発揮してもらうことで、組織全体の力を引き上げる――そうした視点で配転を捉えることが、今後の企業運営においては不可欠です。
経営者や人事担当者は、「法的に可能か」だけでなく、「経営戦略として妥当か」「社員にとって納得感のある判断か」といった視点を持ち、配転を一つの組織戦略として機能させていく必要があります。法務と人事、そして経営の視点を統合した対応こそが、これからの時代に求められる企業の姿勢です。
問題社員への対応に迷ったら専門家に相談を
ここまで見てきたように、配転や職種変更に応じない社員への対応は、単に「命令すればいい」「従わなければ処分すればいい」といった単純な問題ではありません。法的な判断だけでなく、経営的視点、社員個人の事情や価値観への理解、そして職場全体への影響など、多角的な観点から慎重に対応する必要があります。
特に、一般に「モンスター社員」とも言われるような問題社員の対応は、企業にとって非常に頭の痛い問題です。命令に従わない、指導に反発する、業務命令を拒否するなど、企業秩序を乱す行動が見られたとしても、対応を誤れば労働トラブルへと発展し、企業側が不利な立場に立たされることもあります。
そのため、対応にあたっては、事前の事実関係の整理や記録の蓄積、社員とのコミュニケーションの記録、業務上の必要性の明確化などを丁寧に行う必要があります。さらに、命令に応じない理由を聞き取り、個別事情を把握したうえで、どう対応すべきかを慎重に検討するべきです。
とはいえ、実務上は一つひとつのケースに時間や手間をかけることが難しい場合もあるでしょう。だからこそ、問題が複雑化する前に、専門家に相談することが有効です。特に、法的リスクや手続きの適正さを踏まえて、対応方法をアドバイスできる弁護士の存在は心強いものです。
四谷麹町法律事務所では、問題社員への対応に関して、個別の注意指導の仕方や懲戒処分の進め方、社員への対応方法について、具体的かつ実践的なサポートを行っています。さらに、状況に応じては、企業側の代理人として、問題社員本人や、相手方代理人弁護士との交渉にも対応しています。
訴訟や労働審判に至る前の段階から、適切な対応を行うことで、企業側の負担を軽減し、トラブルの早期解決を図ることが可能です。配転命令や職種変更に応じない社員の対応にお困りの際は、企業側専門の経験豊富な四谷麹町法律事務所に、ぜひ一度ご相談ください。