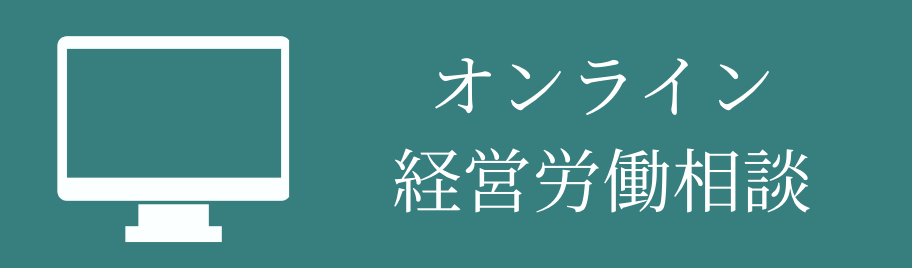期待通りに活躍できない社員への対応法|育成・配置転換・退職勧奨まで会社経営者が取るべき判断とは

目次
動画解説
パフォーマンスが期待レベルに達しない社員への基本的な考え方
会社経営者にとって、社員が期待していたパフォーマンスを発揮できていないという状況は、日々の業務の中でしばしば直面する課題です。採用時には適性があると思っていても、実際に業務を始めてみると、思ったように能力を発揮できないケースは珍しくありません。
こうした場面で重要なのは、「すぐに見限るか、それとも育成するか」という二択で考えるのではなく、まずはその社員にどのような可能性があるのかを冷静に見極める視点です。能力不足や業務の理解不足が見られるからといって即座に排除するような対応は、結果として組織に悪影響を及ぼすリスクもあります。
一方で、「時間をかければ誰でも育つ」と安易に期待しすぎることも、育成担当者の過剰な負担につながり、会社全体の効率を損なう原因になります。つまり、社員本人の適性や成長の見込みを見極めながら、会社としてどこまで対応するのか、その限界と方向性を明確にすることが、経営者に求められる判断なのです。
パフォーマンスが低いという事実だけを問題視するのではなく、「なぜそのような状況になっているのか」「どのような支援や環境があれば改善する可能性があるのか」といった観点から状況を丁寧に把握することが第一歩です。そしてそのうえで、必要に応じた育成支援、適正配置、最終的には退職支援といった段階的な対応方針を立てていくことが、健全な組織運営には不可欠です。
原因は会社側か、社員本人かを見極める視点
社員のパフォーマンスが期待に届かない場合、その原因がどこにあるのかを見極めることは、会社経営者にとって極めて重要な判断材料となります。問題の所在が会社側にあるのか、あるいは社員本人にあるのかを正確に切り分けなければ、誤った対応によって組織内にさらなる混乱を招く恐れがあるからです。
まず会社側に原因があるケースとしては、教育や支援体制が不十分であることが挙げられます。入社後の業務引継ぎが曖昧だったり、マニュアルが整備されていなかったり、周囲のサポートが機能していない場合には、能力のある社員でも本来の力を発揮することができません。このような状況では、社員の責任を問う前に、会社としての体制の見直しが必要です。
一方で、社員本人に原因がある場合も当然あります。明らかに業務遂行能力が不足している、基本的な報連相ができない、注意しても同じミスを繰り返すといったケースでは、教育しても伸びる見込みがあるのかどうかを冷静に判断しなければなりません。
このような場合、重要なのは「どこまでが会社の支援でカバーできる範囲か」「どこから先は本人の資質や努力に委ねられるか」という視点です。会社が支援を尽くしたにもかかわらず改善が見られない場合は、社員本人の適性や職務能力に限界があると判断せざるを得ません。
原因の切り分けは、単なる責任の押し付けではなく、今後の対応方針を決めるうえでの出発点です。どちらに原因があるのかを明確にしたうえで、会社側として行うべき改善と、社員本人に求める努力を整理し、最適な対応につなげていくことが、的確なマネジメントの第一歩となります。
適性がない場合の育成の難しさと前提理解
社員のパフォーマンスが上がらない要因の一つに、「その業務に対する適性が根本的に欠けている」というケースがあります。会社経営者として、このような状況に直面したとき、単に「育てれば伸びるはずだ」という前提で対応し続けることには注意が必要です。
たとえば、論理的思考が求められる仕事に対して、感覚的な処理しかできない社員、対人対応が必須の業務に対して極度の対人ストレスを抱える社員など、その人の持つ特性と業務の本質的な要求がかみ合わない場合、いくら時間と労力をかけて育成しても、期待される水準まで到達しないことが少なくありません。
このような「適性の不一致」は、本人にとっても強いストレスとなり、心理的な負担が蓄積していくことで、メンタル不調や職場定着の困難につながるリスクもあります。その結果として、周囲の社員への負担が増し、職場全体の効率や士気を下げる要因にもなりかねません。
そのため、会社経営者は「育成の前提として、一定の適性が備わっているかどうか」を見極める視点を持つことが不可欠です。初期段階での見極めが遅れると、指導担当者やチーム全体に不必要な負荷を与える結果となり、企業全体の成長を妨げることにもなり得ます。
社員の成長を信じて育てる姿勢はもちろん大切ですが、それが「適性を無視した思い込み」になっていないかを常に点検する必要があります。冷静な判断と、適性を前提とした育成方針の見直しが、結果として組織にとっても本人にとっても最善の選択となるのです。
教育・指導の基本は「具体的な支援」から始める
社員の能力不足や業務不適応が明らかになったとき、会社経営者としてまず行うべきは、「具体的な支援」による教育・指導です。抽象的な叱責や精神論ではなく、現実的に改善につながる手立てを講じることで、成長のきっかけを与えることができます。
たとえば、「もっと頑張れ」「もっと早くやってくれ」といった言葉だけでは、本人にとっては何をどう変えれば良いのかが分かりません。指導の効果を高めるためには、「どの業務をどの順序で行うか」「どのような基準で判断するか」といった、具体的かつ実務に即した説明が必要です。
また、業務の全体像を把握できていない社員に対しては、作業の流れを可視化したり、チェックリストを用意するなど、視覚的な支援も有効です。業務マニュアルやトレーニング資料を整備し、指導担当者だけに依存しない体制を構築することも、企業として取り組むべき支援の一つです。
さらに、業務の習熟度に応じてタスクの難易度を調整し、徐々にレベルアップしていけるような支援環境を整えることが、本人の自信とやる気につながります。初めから高い成果を求めすぎるのではなく、「まずは確実にできることから始める」というステップを踏ませることが重要です。
会社として具体的な支援を実行したという事実は、仮に今後の対応で配置転換や退職勧奨を検討する場合にも、その正当性を裏付ける根拠となります。つまり、経営者にとっても「誠実な対応」を記録として残すことが、リスク管理の観点からも非常に有意義なのです。
教育・指導は、本人任せにせず、会社として「何をどう支援したか」が明確でなければ効果を持ちません。抽象的な言葉ではなく、実際に行動を変えるための仕組みを提供することこそが、教育の出発点です。
できる仕事から段階的にレベルアップを図る
業務遂行能力に課題を抱える社員に対しては、「できないことを無理にやらせる」のではなく、「できることから始めて段階的にレベルアップを図る」という考え方が基本です。これは、本人の成功体験を積み重ねることで自信を育て、モチベーションの向上につなげるとともに、組織としても業務の確実性を高める効果があります。
いきなりすべての業務を一人前にこなすことを求めるのではなく、まずは単純で明確なタスクから取り組ませ、少しずつ責任範囲を広げていく。例えば、資料のコピーやファイリング、簡単な入力作業などの補助的な業務を正確にこなすことからスタートし、業務の流れを体得させることで、次の段階へのステップを築きます。
このように段階的な対応を行うには、業務内容を細分化し、それぞれの難易度と習得目標を明確にしておく必要があります。加えて、定期的に評価の場を設け、「何ができるようになったか」「次に何を習得するか」を本人と共有することで、育成の進捗を双方が認識できる仕組みが重要です。
段階的な成長を促すためには、社員の小さな進歩を見逃さず、適切なフィードバックを与えることも欠かせません。「前回よりも正確にできている」「報告のタイミングが早くなった」など、具体的な変化を指摘することで、本人にとっても成長実感が生まれやすくなります。
経営者としては、「結果」だけでなく「成長のプロセス」に注目する視点を持つことが求められます。組織の中で一人ひとりが段階的に成長していけるような体制を整えることが、結果として企業全体の底上げにつながります。焦らず、しかし着実に成長させる姿勢が、長期的には最も実効性のある育成手段となるのです。
育成担当者の負担を軽視せず、会社が報いる体制を整える
社員の育成は、本人にとって成長の機会であると同時に、それを支える育成担当者にとっても大きな労力を伴う業務です。とくに、能力や適性に不安のある社員を一から指導するとなれば、その負担は通常以上に重くなります。会社経営者として、この負担を軽視することは避けなければなりません。
育成担当者が行っていることは単なる「指導」ではなく、業務の進行と並行して相手に寄り添い、理解度を確認しながら、時には精神的なフォローまで担っている極めて高度な役割です。それにもかかわらず、「教えて当然」「できて当然」という空気が社内に蔓延すれば、育成担当者のモチベーションは著しく低下し、やがて離職やチームの崩壊を招くことになります。
そこで会社として必要なのは、育成にあたる社員の貢献を正しく評価し、それに見合った処遇やサポートを行う体制を整えることです。たとえば、育成に関わる時間を業務評価の一部として明確に反映させる、育成対象者との面談記録を評価資料に組み込む、チーム内で育成の負担を分散させるなど、実務的な配慮が求められます。
また、育成にかかる時間やコストを経営側が「必要な投資」として捉える姿勢も重要です。目に見える成果がすぐに出なくとも、支援を受ける社員だけでなく、育成を担う側の社員も「会社に評価されている」と感じられる環境づくりが、組織全体の健全な循環を支えるのです。
経営者としては、育成対象者の成長だけでなく、それを支える社員のケアにも目を向ける必要があります。育成は、会社の未来を担う重要な営みであると同時に、担当者の努力と献身が支えているという事実を、常に意識しておくべきです。
適性がない社員に求められる「適正配置」の重要性
教育や支援を重ねてもなお、業務に対する理解や遂行能力に限界があると判断される社員に対しては、「育て続ける」ことにこだわるのではなく、「適正配置」によって業務とのミスマッチを解消する方向に舵を切ることが重要です。これは、本人にとっても、組織にとってもより建設的な選択肢となります。
人にはそれぞれ得意・不得意があり、ある仕事で成果が出せなくても、別の分野では力を発揮できる可能性があります。現場での判断が求められる業務が苦手な社員でも、正確さが重視されるルーチンワークや、裏方的な業務では高い集中力を発揮することがあります。このように、「できない」ではなく「向いていない」という視点で社員の現状を見直すことが、会社経営者にとって必要な発想です。
適正配置を行う際には、業務内容だけでなく、チーム構成や指導体制、本人の希望やストレス要因など、総合的な観点から検討することが求められます。また、「異動=降格」というような負の印象を与えないように配慮し、あくまで能力を発揮できる環境を整えるという前向きな意味での配置転換であることを本人にも丁寧に説明する必要があります。
適正配置は、一人の社員の再生を図るだけでなく、チームの負担軽減や組織全体の効率化にも寄与する可能性を持っています。だからこそ、会社経営者には、社員の現状に対して柔軟に対応し、機動的に人材を配置する力が求められます。
育成に行き詰まりを感じたとき、それは終わりではなく、新たな配置の機会かもしれません。社員の可能性を信じ、最適な場所で力を発揮させることが、経営者としての大切な役割の一つです。
社内で適正配置が難しい場合の退職勧奨と転職支援
育成や適正配置を検討しても、どうしても会社内での活躍が見込めないと判断される社員については、最終的に退職勧奨を検討する必要があります。この判断は、本人にとっても組織にとっても負担の大きいものですが、経営者として避けては通れない重要な対応の一つです。
退職勧奨を行う際には、感情的な判断ではなく、これまでに行った教育・指導・配置転換の経緯を踏まえた、客観的かつ誠実な説明が欠かせません。なぜ退職を勧めるに至ったのか、これ以上会社として支援を継続することが現実的ではないことを、相手の人格を否定することなく丁寧に伝える姿勢が必要です。
また、単に「辞めてほしい」と伝えるのではなく、本人の将来にとってプラスとなる転職の機会であることを強調し、必要に応じて職業紹介やキャリアアドバイザーの紹介など、実際の支援も併せて行うことが望まれます。本人にとっても「見放された」のではなく、「新たな道を後押しされた」と感じられるような対応が、円満な退職とその後の前向きな人生設計につながります。
このような対応を適切に行うためには、記録の整備と事前準備が不可欠です。いつ、どのような指導を行い、どのような反応があったのか。配置転換の提案をどのように受け取ったのか。こうした情報を整理したうえで話し合いに臨むことで、感情的な対立を避け、建設的な合意形成が可能となります。
会社としても「社員を使い捨てにした」と思われないような対応を心がけることが、他の社員へのメッセージにもなります。退職勧奨はあくまでも最終手段であり、その過程と姿勢こそが企業としての信頼性を問われるポイントとなります。経営者には、その場しのぎの判断ではなく、中長期的視点での対応が求められるのです。
試用期間中の見極めと対応の法的な位置づけ
新たに社員を迎え入れた際、会社としてはその社員が組織に適応し、期待される業務をこなせるかどうかを見極める期間として「試用期間」を設けることがあります。会社経営者にとって、この期間は「本採用に進むかどうか」の重要な判断を下すための準備期間です。
試用期間は、単なるお試し雇用ではなく、正式な労働契約のもとに勤務している状態であるため、法的にも一定の保護が及びます。したがって、「思ったより能力が低いから」「雰囲気が合わないから」という曖昧な理由だけで簡単に解雇できるわけではありません。労働契約法や判例上、「解約権の濫用」にあたると判断されれば、不当解雇とみなされるリスクがあります。
そのため、試用期間中であっても、指導や教育の記録、具体的な業務能力の評価、本人へのフィードバック内容などをしっかりと残しておくことが重要です。そして、問題点が明確であり、それを改善する機会を与えてもなお、職務遂行が著しく困難であると判断される場合に限って、本採用を見送るという決断が認められやすくなります。
また、試用期間の設定自体が就業規則や労働契約書に明示されていなければ、後から「これは試用期間だった」と主張することはできません。形式だけでなく、運用面でも明確な位置づけと実績が求められるため、採用時点からの準備が欠かせません。
経営者としては、「入社後すぐに使えなければ辞めてもらう」といった安易な対応ではなく、試用期間を活用して、丁寧に見極めるとともに、適正な判断を下せるよう、準備と記録を怠らないことが求められます。法的リスクを回避しつつ、組織の健全性を守るうえでも、この期間を形式的なものにせず、実質的に活用することが重要です。
才能が発揮できる仕事に就けるよう配慮するのも経営者の責任
社員一人ひとりが本来持っている能力や特性を活かし、最大限に力を発揮できる職場環境を整えることは、会社経営者に課せられた重要な責務の一つです。すべての人材が万能である必要はありません。むしろ、適切な場所で適切な役割を与えることによって、初めてその人の才能が表面化するというケースは多くあります。
そのため、ある仕事で成果が上がらないからといって即座に「不適格」と判断するのではなく、「この人が最も力を発揮できるのはどの場面か」という視点を持つことが大切です。コミュニケーションが苦手でも、コツコツと正確な作業を得意とする社員は管理業務や分析業務で力を発揮することがありますし、要領は悪くても誠実で信頼されやすい人材であれば、対外的な調整役として力を伸ばす可能性もあります。
このような視点を持つには、普段から社員一人ひとりをよく観察し、何にストレスを感じ、何にやりがいを見出しているかを把握しておく必要があります。また、年齢や職歴に関わらず、「新たな役割に挑戦するチャンスがある」という文化を育てることも、才能を発見しやすい組織づくりにつながります。
経営者自身が柔軟な発想で社員の能力を見極め、「この人にはこのポジションが合うのではないか」という仮説を持って配置を行うことは、単なる人事戦略にとどまらず、組織の活性化や離職率の低下にも直結します。
人材の多様性を活かすとは、個々の能力差を許容することではなく、それぞれの才能が発揮できる場を用意することです。経営者がそのような視点を持って組織をデザインしていくことで、社員もまた「自分の居場所がある」と感じ、主体的に業務に取り組むようになります。才能を見出し、活かすこと――それこそが、持続可能な組織づくりの原動力となるのです。